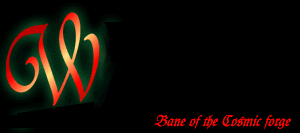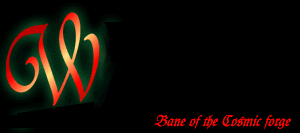再びお城にやって来た。勿論あの底が見えない、想像しただけでも恐ろしくなってく
る渓谷をロープで渡って。
二度と渡りたくないと思ってたのに・
でも、そんなわがままも言っていられない。再び私は必死の思いで渡ってきた。
そして、今度こそもう向こう側に渡ることはないようにと祈ってる。
ピラミッドで休憩をしている間に彼女たちの保存食を見つけ、ごっそり持ってきてしま
った。
村には行けなかったけど、これで当分、食料には事欠かさない。最も、温
かい料理ってわけにはいかないけど。例のごとく、干し肉や乾燥野菜、炒り米などだ。
そして、地下2階のまだ開けてない門の前に私たちは来ていた。
カギ穴もなければなんにもない。内側にはドアが見えるのだけれど。
「でっとぉ・・・魔法使いの住処をさぐれったって、多分、ここがそうだとは思うんだ
が・・どうやって入るんだ?どうせなら門の開け方も教えてくれりゃよかったのに!
あの蛇やろう、いらんことばっかぺらぺらしゃべりやがって、肝心な事は言わねぇんだ
からな!」
ピアースが門のあちこちを調べながら呟いた。
突然、ホトがはっとしたように慌ててバッグの底から何かを取り出した。
「それらしき物って言えばゾーフィタスのとこで見つけたこの指輪・・これなんか怪し
いんじゃないかい?髑髏の指輪!!もし魔法でロックしてあるとしたら・・・これで
解除できるかもしれないよ!?」
「そうだなぁ・・多分ここはあいつの部屋だったんだろうから。だけどどう使
えばいいんだ?」
ホトから指輪を受け取り、ピアースは、難しい顔をして、指でつまみ裏側を見たり髑髏をじっと見た
りしている。
「指輪なんかどうすりゃいいんだ?差し込むところもないし・・おい、髑髏、この
ドア開けろ!」
使い方がわからずピアースは、やけっぱちと言おうかふざけてと言おう
か、髑髏の指輪を門につきつけた。
−ギ、ギ、ギ、ギ、ギィーーーーー・・・・・−
一瞬髑髏が光ったかと思うと門がひとりでに開き始めた。
「あ、あれ?開いちまいやがったぜ!」
「へ、へん、やっぱしね!!あたいの思った通りだ!!」
ホトは得意満面。
「さ、入ろう!!」
「何これ?猫に注意って?」
魔法使いの部屋と書かれているドアには注意書きもあった。
「猫ってあの猫だろ?なんなんだろ?入ると猫に引っ掻かれるのかな?」
「こっちにはその親戚がいるんだから大丈夫だろ?」
「どういう意味さ、それ?」
ホトがターマンをきっと睨んだ。
「別に、深い意味はないさ。頼りになるって事・・だな。」
まだ睨み続けているホトを無視しターマンはドアを開けた。
中は物音一つせず平和だった。
「べっつにどぉってことないじゃん。でも、わざわざ書いてあるんだからその辺に隠れてる・・とか。」
ホトがターマンの後ろからドア越しにキョロキョロ中の様子をうかがった。
「脅しか、さもなきゃ飼い主がいなくなって死んだ・・とか・・な。」
そう言いながら奥へ進んだターマンを黒いそして巨大な影が襲った。
「ミギャァーオーーーーー、、、」
とっさに刀を抜きその影に一降りするターマン。
が、影は簡単にそれを避けるとスタっと着地した。
それは、確かに猫・・だった。
でも大きいなんてもんじゃない。2mほどはあろうかと思う黒猫だった。
その長いしっぽをゆっくりと振りながら、じっとこちらを見ている。
ギラギラと怒りに燃えた金色の目。人間など一裂きで殺せそうなするどい爪。おまけに
身体全体に真っ赤な炎をまとっている!!
彼は静かに攻撃態勢を取りながらじっとこち
らの様子を伺っている。
「なるほどな、書いておくわけだ。地獄の炎を背負った悪魔猫ってわけ・・か。」
「感心してる場合じゃだろ、ピアース?」
「まっ・・な。」
少しでも隙をみせると飛びかかってきそうだ。しばらくにらみ合いが続いた。
と、突然 「ゴオーっ!!」と部屋一面が真っ赤な炎に包まれた。
私達は散り散りになりなんとか炎を避けた。
「あ、あぁーん、もうっ!ごげちゃったじゃないかぁ!あんたも猫ならこの毛並みがど
んなに素敵かわかるだろ?!アホっ!!」
ホトが左手で自慢のしっぽを持ち右手でその
少しちぢれてしまった毛を撫ぜながらHELL−CATに文句を言った。
「自分でも認めてるんじゃないか。」
ターマンがそれみろと言うように吐いた。
「うるさいよっ!あんたにこの気持ちがわかるかいっ!」
「はっ、わかりたいとも思わないね。」
きっと睨んだホトを小馬鹿にするようにターマンは両腕を少し広げ首をすくめた。
「おいおい、もめてる場合じゃないだろ?」
ピアースがそう言った瞬間だった。HELL−CATが一声鳴いたかと思うと再び辺りは火の海となった。
「もうっ!火炎放射器だね、全く!」
「言っとくけど、ターマン、あたいはこんな悪魔に魂を売った猫を親戚に持った覚えは
ないよっ!確かに先祖は猫だけどさ、こいつは只の猫又で、あたいたち誇り高いフェル
プール族とは全く違うんだよ。しっかり覚えときな!」
炎のブレスを避けながらそれで も文句を忘れないホトだった。
「どうだか・・・・・」
同じく炎からさっと身を避けながら返答するターマン。
「2人ともいいかげんにしてよね!真面目にやってよっ!」
思わず私は、大声で怒鳴ってしまった。
そう、私は2人のように上手く避けることができず全身に火脹れを作っ
て、それでもなんとか部屋の隅に身を寄せていた。
ハートレーがヒール・ウーンズの魔法で治してくれてはいるのだけれど、いつ次の攻撃が来るとも限らない。
「だってさ・・」
ホトは不満げに呟くとスピアを持ちなおした。アマズール族の女
王を倒した時、手に入れた死のスピアだ。
これは普通のスピアとは違い片手で持てるの
で、もう一方の手には楯が握られている。うまくいけば一撃で死に到らしめることがで
きるという優れもの。
「そんじゃぁ、まぁ、本気になろうかねぇ・・・。」
「同族だからって手加減するなよ。」
「あんたに言われたくないね。それに同族じゃないってさっきから言ってるだろ。こい
つは・・・単なる化け猫さ。」
「だから一緒だって言ってるんだぜ。」
2人とも黒猫を警戒しながらも、まだ言い合って いる。
「ホントにいいかげんにしてくださいよ。手を抜ける相手じゃないことくらい、わかっ
ているはずですよ、ホト、ターマン!」
私の火傷を治療し終えたハートレーが口を挟んだ。
「そうそう。」
すかさず私も付け加える。
「おいおい、4人とも適当に一息ついてるなよ!俺とコルピッツにまかせっきりってい
うとこはおんなじだぜ、ツェナちゃん。」
気がつくとコルピッツとピアースがHELL
−CATと悪戦苦闘中である。
その鋭い爪の攻撃を剣で受け止め、コルピッツは酸のブ
レスで、ピアースは隙を見て手裏剣で攻撃している。
「HELL−CATとい言うだけあってしつこいんだぜ、こいつ!」
「ギャオー!」
ピアースの手裏剣が右目に命中した。その痛みで気が狂ったかのように怒りその鋭い牙
を剥き私に向けて突進してきた。
「えっ?えっ?そ、そんなぁ・・・」
突然の事で頭の中が真っ白になってしまった。
呪文が頭に浮かばない!が、その隙を逃す仲間達ではない。
すかさずホトがスピアを投げる。
コルピッツがブレスを吐きかけ、ピアースが手裏剣を投げた。
ハートレーがその狙いを眉間に定め、その重いソードを満身の力を込め投げつける。
そしてターマンは刀を持ち直しHELL−CATに突進し始めた。
そして・・・・・・
「サンキュー、ツェーナちゃん。囮の役目ごっくろうさん!」
倒れたHELL−CATの頭を蹴飛ばしてからピアースは私の方に近づいてきた。
「どうせ私はそれくらいしか役にたちませんよ。」
もう少しで私を頭から呑み込むところだったHELL−CATは目の前で見るも無残な姿を晒していた。
横腹にはスピア、
眉間には深々と刺さったソード、そして酸で溶けかかった身体全体にはいくつかの手裏剣も刺さ
っていた。
「チームワークのなせる技ってやつだね。もっともターマンはなーんにもしてないけど
さ。」
ちらっとターマンを見、スピアを抜きながらてホトが私に笑いかけた。
そんなホトを全く無視しターマンは部屋の奥を調べ始めている。
「しっかし、くっさいなぁ・・・自分で溶かしておいて言うのもなんだけどさ。」
「う、うん、そうね、でも燃やすと余計臭いし・・」
血の臭いと共につーんとする酸と溶けかかった肉・・そのなんとも言えない臭いに私は吐き気を覚えた。でも、なんとか嘔吐を我慢し、私はHELL−CATを呪文でカチンコチンに凍らせた。
その間にピアースは部屋の四方にあった宝箱を調べる。
「まぁまぁの実入りってやつだな。この鍵はどこで使ったらいいんだろ?あと、日記かな、これ?ホト読めるか?こんなへんてこな字、読めりゃしないぜ。」
「どれどれ?」
ホトは日記を受け取るとパラパラとページをめくる。
「多分・・あの魔法使いのおっさんの日記だろうね、これ。」
そう呟くと見入るように読み続けた。
「ホト、ねぇ、ホトったら!何が書いてあるの?」
なかなか内容を教えてくれないホトにしびれをきらし、私はホトに聞いてみた。
「ねぇったら!」
「あっ、ああ、ごめん。つい・・・ね。」
ホトの顔つきはだんだん怒ったものになってきた。
「何が書いてあったの?」
「う、うん・・つまり、実験をしていたってことなんだ。」
「実験?何の?」
「人体実験さ、不老不死の為の。」
「不老不死?」
「ん、最初こいつは死体の再可動を試みたんだ。つまりぃ、ゾンビって訳かな、魂はな
いんだから。それから次には、打ち首になった牧師の魂をあの世にいけないように
呪文をかけ、霊封じの呪文でこの城の尖塔に閉じ込めたんだってさ。最初のゾンビも尖
塔に閉じ込めてあるらしいよ。んとにこんな事は、やっちゃいけない禁断の試みなんだ
よ。神への冒涜だよ!全くなんてやつだ!あんなふうになってたのも自業自得ってやつ
だよ。」
「ってぇことは、この鍵は尖塔の鍵ってわけだな。」
ピアースが鍵を見ながら言った。
「ん、そうらしいね。それから、あのミスタファファスのことも書いてあるよ。
勿論『コズミック・フォージ』とかいう訳のわかんないペンのこともね。それと、後ろ
の方のページは真っ白で、日記の最後には、『王を終わらざる死に誘ったから、呪いか
ら逃れられるはずだ』って事と、『今宵自分の運命をそのペンで刻み込む』って書いて
あるんだけど。後がないってことは結局呪いがかかって、ああなっちゃったんだ
ろうねぇ。」
「そうだろうな。」
「おい、隠しドアだぜ。」
みんなで深刻になってるところにターマンの大声が割り込んだ。
その声ではっとし、それぞれ気を取り直して、隠しドアへと向かった。
ドアを開けるとどうやら物置のようだと判断できた。
そこの壁のボタンを押してみると新たな隠しドアが開いた。
そこで、いろいろ実験をしていたらしく、テーブルの上は様々なポーションの瓶と
薬品の山で一杯だった。
「下手に触らない方がいいですよ。」
とハートレーが言いかけた時には、もうすでにホトがその赤や黄色や青の薬品を混ぜていた。
「う〜ん、なかなか綺麗な色になるねぇ・・・」
とその瞬間だった、
−ドッカア〜〜ン!!−
部屋中に煙が立ち込める。
「ホトっ、大丈夫?」
ゲホゲホむせながら手でその煙をかきわけるようにしてホトのいる方に近寄った。
「ん・・・・大丈夫みたい・・・。」
煙の中から爆発で真っ黒になった顔が見えた。
「ああ、よかった!」
私はほっと胸を撫で下ろした。
「ごめん、ごめん、点火棒いじったらいきなり爆発するんだもん。」
少し照れ臭そうに、その真っ黒になった顔を崩した。
「全くホトは!何にでも興味を持つことはいいんですが、もう少し慎重に願いたいもの
ですよ。」
ハートレーがヒールの魔法をホトにかけようとしながら文句を言った。
「ヒールの魔法くらいあたいでもかけれるよ、余計な御世話だよっ!」
ハートレーの手を振り払うようにして、ホトそっぽを向いた。
「それに、そう大したこともないよ、そりゃ、ちょっと爆発にはびっくりしたけどさ、
上手い具合にこっちにはあんまり被害がなかったから。煙だけですんだみたいだし。そ
れにさ・・・見てみてよ、そのお蔭で奥の壁が落ちでどっかと繋がったみたいだよ。」
話しているうちに気付いたとでもいうように、壁を指差した。
「ホントだ!」
少しずつ煙も薄れてきてテーブルの向こうの壁が見えてきた。人間1人
なんとか通れるくらいの穴が開いている。
ホトは煙で真っ黒になっている事も気にせず
崩れ落ちた壁の向こう側に入って行った。
私達はホトの報告をじっと待つ。
しばらくしてホトは顔を手で整えながら戻って来た。
「どうやら採掘場と繋がったみたい。これでもうあの渓谷を渡らなくてもいいってわけだね。・・・あっ、でも今のところ行く必要もないけどさ。」
「採掘場ですか・・・なるほど。」
ハートレーが1人で納得したような言い方をした。
「じゃ、そろそろお次へ行くとするか。」
その声でピアースの方を振り向くと、ちゃっかり宝箱を開けてそのお宝を手にしている
彼の姿が目に写った。
「スクロールが3つだけだったがな。」
私の視線でわかったのか、スクロールを見せる
とバッグにしまった。
「じゃ次はぁ、どっちにする?尖塔?それとも髑髏のドアを開ける?」
ホトが目をくりくりさせながら言った。
「髑髏のドアはすぐそこなんだから、開けてみようぜ。」
もう決めた!とばかりの口調で、ピアースが言った。
髑髏の指輪に髑髏のドア・・・もしかして、これからが本番?
そう思ったら、背筋がぞくっとした
|