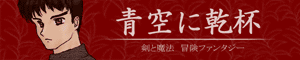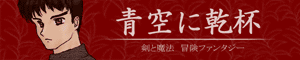|
「ん?・・・・ここ・・は・・・?」
久しぶりの聖魔の塔。そこでの探索を楽しみ、塔の外へ出たつもりのカルロスとミルフィーは、周囲の景色が違うことに気づく。
「トムート村への道が続いてる景色じゃないことは確かね。」
「あ、ああ・・・・・。」
いつもなら聖魔の塔から出ると遠くに森の見える草原が広がり、聖魔の塔の膝元であるトムート村への1本道が続いているはずだった。が、そこは何もない岩山の中腹らしく、その切り立った岩肌を裂いたような細い道があるのみ。
「カルロス?」
何かを考え込んでいるようなカルロスを、ミルフィーは不思議に思って見つめる。
「あ、いや・・・・・つまり・・」
「もしかして、カルロス、ここを知ってるの?」
「あ・・ああ・・・ひょっとしたら、なんだが・・・。」
「カルロスの故郷っていうか世界だったとか?」
ミルフィーのその言葉に、目の前の景色をじっと見つめていたカルロスはぎくっとしたように彼女を見つめる。
「え?ホントにそうだったの?」
ふと思いついたことを軽く口にしたつもりのミルフィーは、カルロスのその反応に驚く。
「確証はないが・・・確かに似通っている。が、同じような場所もありうるからな。」
「そうよね?」
「確信するためにはもう少し情報が必要だな。麓まで行ってみるか?」
「そうね。」
世界が違ったからと言って出てきたばかりの塔へまた入る気にもならなかった。それに、もしもここがカルロスの世界なら興味があった。加えて縛られるものはなにもない2人にとってはどの世界だろうとさして関係はないのである。あるとすれば老婆やレオン、レイミアス、そしてチキとシャイくらいなのだが、別にこれで二度と会えないわけでもないはずだった。そう、ミリアにもらった炎の指輪を火に投げいれば、すぐにでも帰ることができる。それは確かな保証であり、聖魔の塔のトラップなどでどこへ飛ばされても安心していられる余裕の元。もっともどこへ飛ばされようとそこでの冒険をエンジョイすればいいのだから、転移のトラップもたいして気にしてない2人ではある。
−ひゅ〜〜〜〜〜・・・−
「な、なに?この絶壁?こんな細い道を行けっていうのぉ?」
それはまさに切り立った岩山だった。岩がゴロゴロとむき出している道を進み山腹をでた2人の目の前に広がる景色は・・まさに、絶景かな!だった。
周囲には他の山も何もなく、青空と太陽、そして、眼下には見事な雲海がひろがっていた。そして、岩山の岩肌をぐるっと巻くように細い道が下へと続いている。しかも岩壁にぴったりと背中を合わせ、横に足をずらすようにして進まなければならないような道である。もちろん下が見えるわけはない。落ちたら命はないことだけは確かである。
「多分・・間違いなくオレの世界だろうな。」
「カルロス・・こんなところを登って来たの?」
「何度落ちそうに、いや、足を滑らせてもうダメだと思ったか知れないな。・・・道も結構もろくてな・・・崩れやすいんだ。もっとも麓までこんな道が続いているわけじゃない。途中までなんだが。」
「そ、そう・・・・・。」
「恐いか?」
「誰に言ってるのよ?」
「ははは・・そうか?」
きっと睨んで反論したミルフィーに、カルロスは軽い笑みをみせた。が、その笑顔が普段のものと違うと感じたミルフィーは、カルロスをじっと見つめる。
「カルロス?」
「なんだ?」
ミルフィーは老婆の言葉を思い出していた。
『家柄、身分、能力、どれをとっても申し分のない男なんぢゃ。』
「何かあったの?」
「何か・・とは?」
「・・・あなたの故郷・・・つまり、家で?」
「ミルフィー・・」
心配そうな表情で問いかけたミルフィーの頬をそっと両手で包み込み、カルロスはふっと笑う。
「話さないわけにはいかないだろうな?」
「当然でしょ?話さないですむと思うの?」
「ここじゃ腰を下ろしてゆっくりとってわけにもいかないな。戻ろうか?」
一応聖魔の塔入口周辺は岩ばかりといってもそれなりの広さなので、腰をかける場所くらいある。
「そんなに長い話?」
「ああ、長いぞ。オレの背負っている過去だ。」
「ふ〜〜ん・・それって何人落としたかっていう話?」
「ミルフィー・・・」
カルロスが名実共に女殺しであったことは知っていた。が、その話がそんなことではないことはミルフィーは十分承知していた。だがあまりにも深刻そうなカルロスの様子に、ふと悪戯心がその言葉を口にさせ、そしてカルロスは、単にふざけて茶化したのではなく、気を楽にさせるためのものだと理解していた。
「まー・・そんなとこかもしれん。」
「え?本当に?」
苦笑いをしながら答えたカルロスの言葉に驚いたのはミルフィーの方だった。
「もう・・・おどかすんだから・・・」
が、カルロスの悪戯っ子のような笑みに、どうやらそうでもなさそうだ(当たり前だが)と思ったミルフィーは、口を尖らせて文句を言う。
「妬けたか?」
「あのね・・カルロス!」
−グギャアー!−
「コンドルだ。」
目の前に餌を見つけたよろこびで目を輝かせた巨大な怪鳥が羽ばたいていた。
「コンドル?」
「ああ、だが、食肉種であるということと、この大きさでな、この山に棲む怪鳥として有名なんだ。細く険しい道とこいつのおかげで、悠久の昔から聖魔の塔へたどり着いた者は数えるほどだと・・いや、いないとも言われている。」
それももっともだと思われた。その全長約8mほど。たとえこれほど大きくなくとも、足場の悪いところで戦うのは不可能だと思われた。
「ふ〜ん・・・向こうとはぜんぜん違うのね。」
なだらかな草原に囲まれているミルフィーの世界にある聖魔の塔、つまりあちこちの異世界にあるという塔への入口の1つは、本当に穏やかである。近くに冒険者たちの憩いの村ともいえるトムート村もある。1歩中へ入れば危険に包まれるが、外はいたって平和なのである。
「だが、こう偶然が重なることもまずないだろう。おそらくここはオレの世界だ。」
「なるほど。」
−グギャアー!−
「なんだ、オレを忘れたのか?」
「え?」
余裕なかまえで話している2人を襲おうとした怪鳥に話しかけたカルロスに、ミルフィーは驚く。
「こっちではあれから何年経ってる?全く経ってないということもないだろ?卵は無事孵ったか?雛は元気か?」
−グギャ?−
どうやらカルロスに見覚えがあることを思い出したらしく、鋭い爪で2人を捕まえようとしていた怪鳥はそれを止めて首を傾げる。
「キングスネークはもう他にはいなかったか?」
−ギャオーーース!−
嬉しそうに目を細めると、怪鳥はひょいっとその大きなくちばしでカルロスとミルフィーをすくうようにして挟んだ。
「え?・・・ち、ちょっと・・・・」
「大丈夫だ・・・・多分な。」
「多分なって・・・カルロス?」
カルロスがあまりにも親しげに(?)話していて、油断していた。普通ならそんな隙はみせないミルフィーである。
−ヒューーーーーー・・−
2人をくちばしで挟んだまま、怪鳥は向かい風を切って山頂へと飛ぶ。
あっという間に山頂に着くと、平らなそこへ2人を置く。
−グギャ?・・ギャーース!−
「え?」
その2人を見つけた巨大な雛鳥が嬉しそうにかけよってくる。
−ツン!−
ひょっとして餌にされる?とミルフィーがぎょっとして見つめる中、怪鳥が2人の手前でその雛鳥をくちばしではじき飛ばす。
−グギャ!−
−ギャ?!−
そして、2人の目の前でなにやら会話したあと、2羽はそろってぺこぺことおじぎをし始めた。
「こ、これって・・・・?」
半ば呆然としてカルロスを見つめるミルフィー。
「はは・・・やっぱり覚えていてくれたらしいな。」
つまり、カルロスが数年前、聖魔の塔へ行こうと山を登っているとき、当然のように怪鳥に襲われたわけである。そして、あの山肌の道なのである。たとえ如何に腕があろうと満足に戦える状況ではない。その結果、餌として山頂の巣へ運ばれたわけだが、偶然そのときキングスネークと呼ばれる巨大蛇が卵を狙って巣へ侵入してきたのである。つまり、カルロスはそのキングスネークを倒した雛鳥の命の恩人。その恩返しに聖魔の塔の入口までカルロスを運んだその怪鳥・母鳥は、数年経っているであろう今もカルロスを忘れていなかったということらしかった。
ということで、道が道ということで心配だった下山も、母鳥のおかげですんなりと麓へ下りることができた。
そして、麓に広がる広大な森林地帯を抜け、殺伐とした荒野を抜け、砂漠を抜けてようやく人が住んでいる小さな漁師村へと2人は着いた。勿論その間にカルロスは過去の諸事情をミルフィーに話しずみである。
「ここから船でパシャロアの港街まで行き、そこから大型帆船で大海の向こうのリンガロへ渡り、そこでまた別の船で・・・・説明してもなんだな・・・・ともかく港町で航路を変え、大陸を3つ渡ったところがオレの国だ。」
「遠いのね?」
「まーな。」
「この世界には転移の装置とか魔法はないの?」
「残念ながらそういったものはない。一応魔法の類はあるが、ごく一部の特殊な人間でしか使えない。」
「そうなの?」
「ああ、限られた特別な一族、つまり血筋ということだろうな。それに限られているし、その中でも特別な修行を積んだ術師とか魔法使い、賢者といったところだな。」
「ふ〜〜ん・・・・・」
ふとカルロスは悪戯心であることを思い出し、目をかがやかす。
「なに、カルロス?何かたくらんでるでしょ?」
そのカルロスの表情を読んで、ミルフィーがすかさず指摘する。
「分かるか?」
「勿論よ。」
にこっと笑いカルロスは浮かんだ計画をミルフィーに話す。
それはカルロスの国に伝わっている言い伝え、神話時代、危機に陥った世界を救った黄金の剣士と神龍の話。それに扮して行こうというものだった。
「いいの?そんなことして?」
「それくらいしないと命を狙われないとも言えないんだ。オレはいいが、お前を危険な目には合わせたくはない。」
「あら、私なら大丈夫なのに。」
「まー、そうなんだろうがな・・・。」
公爵家の息子であるカルロス。その昔跡目相続を巡っての血で血を洗った醜い争い。それがいやで家を飛び出たカルロスは、今更公爵家へ帰るつもりは毛頭ないが、それでもせっかくここまで帰ってきたのである、気にならないはずはなかった。どうしようかと躊躇するカルロスに、様子を見に行くことをミルフィーは薦めたのだが、その状態が今も続いている可能性はないとは言えない。
ということで、神話の剣士として登場することを提案してみたのだが、そんな派手な登場はいやだ、とミルフィーに断られ、カルロスは苦笑いする。ミルフィーがそういうような派手なことを承知するとは思っていなかったカルロスでもあるが。
「いいじゃない?そんなに急がなくても。」
飛龍に乗っていけば、長い航海とは比べものにならないくらい早く着く。が、考えてみれば急ぐ必要はどこにもない。
だいたいそれならば最初から飛龍にすればよかったのだ。港町まで出る迄ですでに2ヶ月は経っていた。しかも順調に進んでである。
岩山を取り囲む陽の光も射し込めない森、どこまでも続いているように見えた荒野や砂漠、普通なら方向も見失いさまよい歩く結果となるのだが、そこはミルフィーの風術がある。風を感じて森の中は進み、そして、広い荒野や砂漠では風に乗って移動すればよかった。途中襲ってくる猛獣などは2人にとっては、さほど大した敵でもない。
「そうだな・・・ゆっくりと船旅を楽しむのもいいだろうな。」
ミルフィーの言葉に、カルロスは納得した笑みを返す。
「・・・つまり、ハネムーンということだな?」
「ハネ・・・・」
ぽっと頬を赤く染めてうつむいたミルフィーをカルロスは満足そうに見つめる。それまでで2人の間は確定されているのだが、それでもミルフィーのそういったところは変わっていなかった。そこがまたカルロスのお気に入りなところなのでもある。
剣士としての顔と少女の顔に加わった恋人としての顔、そしてカルロスに向けられている心からの笑顔。それはようやく手に入れることができたカルロスの宝物。
−ボォォォォォォーーーーー・・・−
その小さな港町から船で向かったパシャロア。その港から出る大型帆船の上に2人の幸せそうな姿があった。
|