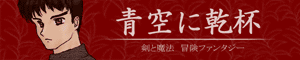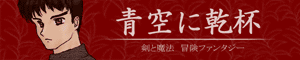|
「ミルフィー・・・」
「なーに、カルロス?」
2人はまだ砂漠の神殿にいた。それは、危険性の危惧もなくなり、ゆっくりとミルフィーを独り占めしたいというカルロスの策略によるものだった。そろそろ帰ろうというミルフィーに、まだ回復が十分ではないから、と断固としてカルロスは帰ろうとしなかった。
そして、そんなカルロスの極度の可干渉さも多少薄れてきた頃、椰子の木陰で一人休んでいたミルフィーにカルロスが歩み寄った。
「ああ、実は砂漠の民から頼まれたことがあるんだが・・」
「何を?」
「彼らは天女様のお力をお借りしたいんだそうだ。」
「天女様?」
「ああ・・・・実はな・・・」
カルロスは照れながら話し始めた。
「オレがお前の眠っていた黄金の花のつぼみをあまりにも必死になって探していた事と・・・それから・・お前を片時も離さそうとしないものだから、花の中から出てきたお前は天女なのだろうと・・・魔王を倒し、天女を救い出したんだろうと、人々の間ではすっかり話が定着しているらしい。」
「え?」
ははは、とカルロスは頭をかいて笑う。
「そんなに必死になって探してくれたの、カルロス?」
「あ、ああ・・・まーな。」
「ありがとう、カルロス。」
「いや、当たり前のことさ。」
カルロスは自分を見つめるミルフィーの瞳をじっと熱く見つめる。
「お前はオレのかけがえのない大切な妻なんだからな。」
「カルロス。」
「それで、天女がどうしたの?」
「あ、ああ・・・そうだった・・。」
長い口づけを交わし、話しかけていた事を忘れてしまったカルロスは照れる。
「実は、ここ数年この辺り一帯の砂漠では水が極度に不足していてだな、ここの神殿も自然の神を祭ってある事から、雨乞いなどもしてるらしいんだが、思うように雨がないらしい。」
「そういえば、そうよね。ここの泉も・・・・水量が少ないわ。泉らしい形跡はあるのに、その半分も・・・ううん、3分の1も満たされてないって感じよね?」
「ああ、そうだ。で、天女様に雨を降らしてもらうことはできないか、ということなんだ。」
「そうねー・・・・・」
「藍の巫女だったお前だ、できるんじゃないのか?」
「でも・・・今は巫女じゃないんだし。」
「だが、知恵の賢者殿も言っておられた・・・精霊の存在は感じられるんだろ?」
「そうね。巫女だった時のように普段でもというわけにはいかないけど、集中すればできると思うわ。」
「では、雨も?」
期待で目を輝かせたカルロスに、ミルフィーは苦笑いする。
「もう引き受けてきたの?」
「あ、いや、もし無理だった場合、彼らを落胆させてしまうことになる。一応聞いてみるとだけ言っておいた。」
「そう・・・・」
しばらくミルフィーは、目の前の泉を見つめて考えていた。
「そうね・・・じゃー、できるかどうかそっとやってみましょ。」
「そっと?」
「ええ。できなかったら悪いでしょ。だから。」
「そうだな。」
2人は微笑みを交わし合う。
「そうと決まったら今晩やってみるわ。カルロス、付き合ってくれるでしょ?」
「今晩?夜にか?」
『夜』という言葉でカルロスは思わずぎくっとする。魔王に連れ去れた時の光景が目に浮かんでいた。
「ダメ?」
カルロスの微笑みが急に陰り、ミルフィーは、どうしたものかと困惑する。
「あ・・い、いや、いいが・・なぜ夜なんだ?昼間でも人がいないところですればいいんじゃないのか?神殿の祭室とかそれにふさわしい場所があるだろ?」
「そうだけど、そこだとどうしても人の目にとまってしまうし、それに、静かなところで彼らとの交信を試したとしても、どうしても人間の生活音が聞こえるのよ。どこかしらから聞こえてくるの。だから、夜の方が成功する可能性が高いと思うの。」
「なるほど。」
しばらくカルロスはミルフィーを見つめて考えてから、微笑む。
「わかった。ただし、オレの傍を離れるなよ、いいな?」
「はい。」
素直に返事をするミルフィーに、カルロスにはまた一段と愛しさを感じていた。
そして、その夜、正殿の奥庭から続いたところにある小さな泉、聖なる泉と呼ばれる泉のほとりに二人は並んで立っていた。
ミルフィーはカルロスと笑みを交わしてからそっと目を閉じる。両手を胸で組み、精神を集中させる。
「精霊王よ、・・・世界に息づく全てのものに生命の糧を与える水の精霊よ、優しさと激しさを持つ精霊の王よ。私の声が聞こえたのならお答え下さい。もし、私があなたの心にかなう者なら、どうかそのお姿をお見せ下さい。・・・あなたのお声をお聞かせください。精霊王よ・・・・やさしき水の王・・・私の声をそして、願いをお聞き届け下さい。どうかこの地に水を。あなたのやさしさで雨の恵みを人々の上にお与えください。」
しばらくすると、音もなく水面に波紋が現れた。
「ミルフィー・・・水が・・水面に波紋が現れたぞ?」
ミルフィーはカルロスの言葉に、ゆっくりと目を開け、その波紋を見つめた。
「世界を救いし女よ、そして藍の神殿の守護騎士よ。そなたらのことは聞き及んでおる。我が異世界にありし友、かの世界の水の王より。」
「水精の王・・・・」
水の精霊王は、小さく呟いたミルフィーににっこりと微笑んで続けた。
「そなたの願いは聞き届けた。今少しで魔王の瘴気により闇に染まるところだった我が身。それを救ってくれたそなたの心に添わぬわけにはいかぬ。」
「ありがとうございます。」
嬉しそうに微笑んだミルフィーの前に、水精の王は、泉を出てゆっくりと歩み寄った。その王は、ミルフィーらの世界の水精の王と異なり、男の姿をしていた。長い髪、長身のやせ形ではあったが、女と言うよりは男の気配を漂わせていた。水色の半透明な身体を長い薄衣で覆っていた。
「女よ、なぜ巫女の座から下りたのだ。そのままならば、かの地の友に頼み、そなたをここへ連れて来ることも可能だったものを。」
「え?」
「何?」
ミルフィーはそれが何を意味しているのか考え、そして、カルロスは焦った。
(ま、まさか・・・魔王の次は精霊王とでもいうのか?)
ミルフィーの腰を抱いて横に立っていたカルロスは、思わずその腕に力を入れる。
「ははは・・・焦らずともよい。」
カルロスに軽く笑ってから水精の王は、再びミルフィーを見つめる。
「冗談だ・・・といっても、まるっきりの冗談でもないのだが・・・。」
「え?」
聞き返したミルフィーを優しく見つめ、水精の王は続ける。
「魔王を倒すことができたのも、そなたのこの男への想い故できた事。私はそなたに倒されたくはないし、嫌われたくもない。」
「え?・・・魔王を倒したのはカルロスなのでは・・?」
怪訝そうな顔で王を見つめるミルフィーと、せっかく忌まわしい出来事を記憶から無くしたのに思い出させてしまう?と焦るカルロス。
「ああ・・・そういうことになるのであろう。そなたをそこまでの気持ちにさせたということなのだから。」
「それはどういう・・・?」
「気にするな、独り言だ。ともかく、雨は降らせよう。その代わり、一つ私の願いを聞いてくれぬか?」
「は、はい・・・私でできることでしたら。」
素直に頷いたミルフィーを、カルロスは焦りを覚えながら見つめる。
「大丈夫だ。おかしな願いはせぬ。」
にっこりと微笑み、水精の王は続けた。
「時が進むに連れ、人間達は我ら精霊のことを忘れがちになってきておる。だが、今回のことで思い起こしてくれる人間も多いだろう。いずれそなたは自分の世界へ帰るのだろうが、年に一度この事を、そして我ら精霊を思い起こすよう、そなたにここへ来てもらいたい。」
ミルフィーからカルロスへ視線を移して王は再び続ける。
「勿論、守護騎士殿も一緒だ。」
「そんなことでいいのですか?」
「そうだ。・・・これをそなたに。」
水精の王が差し出したのは、王の身体と同じように青く半透明の石がついた指輪。
「これをかざし、ここへ来たいと願えば、水鏡が現れ、それを通って来ることができる。道はここへ繋がっておる。」
「ありがとうございます。」
「では、雨と・・・そして豊かな水を約束しよう。ああ、それから、今一つ。水が必要なところでその指輪を翳すがよい。指輪が輝いたところを掘れば水が沸き出るはずだ。」
「細かいご配慮、感謝いたします、水の王。」
「水精の王である私からの祝福だ。新たに宿りし命を祝って。」
「新たに宿り?・・・」
「そうだ。・・・・もしかして、そなた、まだ気づいておらぬのか?」
「え?・・・・あ、あの・・それでは・・」
はっとしたようにミルフィーは自分の腹部に手をあてる。
「ミルフィー?・・ま・まさか・・・」
カルロスもそれを見てようやく意味が分かる。
「この水の王の心よりの祝いだ。受け取ってくれるであろう、天女殿?」
「あ・・はい。・・でも、天女って・・私・・・」
にっこりと笑った王に、ミルフィーは頬を染めていた。
「人々はそう思っておる。その方がありがたみを感じてちょうど良いと思うのだが?」
「そうだな。そういうことにしておけばいいんじゃないか、ミルフィー?」
「・・・カルロスまでそんな事を・・・。」
「いいじゃないか。実際オレにとってはそうなのだし。」
「・・・カルロス!王の前よ?!」
頬を一段と赤く染めて小声でカルロスをたしなめるミルフィーを、水精の王は、暖かい微笑みで見つめる。
「天女を手に入れし勇者か・・・なかなかいいのではないか?魔王を倒し天女を妻にした勇者の話はいつまでも語り継がれていくだろう。そして、その話を思い出すたびに、我ら精霊の事も、また思い出すに違いない。天女殿の友である我らを。」
「王・・・・」
「ではまた会おう。・・・そうだ、できれば産むまでここにいてくれると嬉しいのだが。誕生のおり、改めて祝福を授けたい。」
「ありがとうございます、王。でも・・・・」
「なに、かの地のお子たちは大丈夫だ。それに、簡単に思えても転移は多少なりとも身体に影響がある。不安定な胎児には経験させぬ方がいいと言う者もおる。」
「そうなのですか?」
「実際は知らぬが。」
「ミルフィー、そうさせてもらおう。無理はしない方がいい。」
「カルロス・・・」
「話は決まったようだな。おお、そうだ、天女殿。」
「あ、はい。」
「ここにいる間、我ら精霊の事を、人々の間に改めて広めてもらえまいか?共に同じ世界で息づく仲間の我らの事を。」
「はい、王。喜んで。」
「うむ。」
満足な笑みを浮かべ、水の精霊王は、その姿を水の中へ溶け込むように消した。
「あ、雨が・・・・」
しばらくすると、ポツリポツリと雨が降り始めた。
「濡れるぞ、ミルフィー。神殿へ戻ろう。」
「ええ。」
ミルフィーを抱えるようにして足早に歩くカルロスはいかにも満足げだった。
「あ、雨だ・・・雨が降ってきたぞーーー!」
夜であるにもかかわらず、雨音で起きた者たちによって、神殿のあちこちで、そして、砂漠のあちこちでそんな声が聞こえていた。
「天女殿!勇者殿!」
小走りに神殿に戻った二人を、目を覚ました神官達が出迎える。
「ありがとうございます、天女殿。これで乾きが癒されます。人々の生活に潤いができます。」
「あ、いえ、お礼なら水の精霊王に・・・精霊たちに言ってください。」
「はい、天女殿。」
翌日、小雨の中、神殿の前に広がる広場で、民を集めての神事が執り行われた。共に同じ地に生きる者として、精霊に、自然に、感謝と友情をその祭りで示した。
そして、水の精霊王の言葉に従い、ミルフィーとカルロスは子供が産まれるまでそこに留まることにした。勿論、神殿に仕える者たちも、そして、砂漠の民ダッカートの民たちも、大喜びして承知してくれた。いや、是非留まってほしいと願い出た。
ミルフィーは神殿やオアシスでゆったりとした時を過ごし、そしてカルロスはそんなミルフィーを気遣いながら、時には、砂漠を回り水の指輪を使って水源のある場所を人々に教えたりして、時を待っていた。
そして・・・
「お父様、お帰りなさいっ!」
藍の神殿。嬉しそうに駆け寄るフィーとフィアをカルロスは抱きしめる。
「ああ、ただいま。」
「お母様は?」
「ああ、入口で神官につかまってなにやら話しているが。・・・フィア・・」
「なーに?」
「今度こそ、お前のほしがってた土産があるぞ。」
「え?本当?お父様?」
「ああ、本当だ。母様と一緒だ。」
タタタッ!とフィアは目を輝かせて入口へと走っていく。
「フィア・・ただいま。」
「え?お母様・・?」
「どうしたの、フィア?」
「お母様、・・・若くなったみたい・・・。」
「え?そ、そう?」
「ええ。・・やっぱり好きな人と一緒って、いいものなのね。」
「え・・・?」
(フィ、フィアったら、いつの間にこんな生意気な事を言うようになったのかしら?・・・こっちの方が負けそうだわ。)
思わずミルフィーは赤くなりながら思っていた。
「あ・・・お母様、その赤ちゃんが私の・・・?」
「ええ、そうよ。あなたとフィーの妹よ。」
にっこり笑ったミルフィーの腕の中には、気持ちよさそうに眠る乳児が・・女の子がいた。
「でも、あれだけいろいろあって・・・この子まで産まれたのに、こっちではたったの3週間だなんて。」
「そうだな。オレたちが聖魔の塔へ行った時だからな。」
水の精霊王が時の精霊に頼んでくれたおかげで、2人は向こうの世界へ入ったその時間に帰ってきていた。
「なんでもいいじゃないか。全ては上手くいったんだ。オレもこれでようやくフィアにうるさくせがまれなくてもよくなったし。」
「そうね。」
ふふっと笑ったミルフィーの傍に寄り、カルロスはそっと抱きしめる。
「お前も若返ったし。・・そうだな、今度は男の子がいいな。それから、また、この子にせがまれるかもしれないからな・・次は女の子・・いや、また双子がいいか?フィーとフィアのような。」
ミルフィーを抱きしめたまま、傍らのベッドで眠る我が子を笑顔で見てカルロスは呟く。
「そう簡単に言わないで、カルロス。・・・それじゃ私、何も好きなことできないじゃない?」
カルロスの腕を逃れて、少し機嫌を損ねたような表情でミルフィーは文句を言う。
「いいんだ、それで。いい加減じゃじゃ馬は卒業して落ち着け。」
「そんなのカルロスの勝手よ。私だってたまには気分転換したいわ。私がじっとしていられないのはカルロスだって知ってるでしょ?」
「約束を忘れたのか?」
カルロスは今一度ミルフィーを抱き寄せ、彼女の瞳をじっと見つめる。
「え?どんな約束?」
「・・・・オレのことだけを考えていろと、オレはお前に言った。そして、お前はそれに頷いたんだ。それは、確かな約束だ。」
「え?・・・いつ?・・・私、覚えなんてないわよ?」
「なくても約束は約束だ。」
「そんなの勝手よ、カルロス!」
「だめだ・・・約束だ。」
目の前にカルロスの顔が、熱い瞳があった。その瞳に見つめられ、ミルフィーは何も言えなくなっていた。
「記憶はなくても、お前の心は覚えてるはずだ。・・そうだろ、ミルフィー?」
「カルロス・・・・・・」
なぜだか反論する気持ちはなくなっていた。目の前のカルロスが心が苦しいほど愛しく感じられた。カルロスのやさしいその声が、心の奥底までしみこんでいく感じをミルフィーは受けていた。
「オレの事だけを思っていろ。・・オレがお前のことだけを思ってるように、・・・いつもオレの事を・・・。」
「カルロス・・」
カルロスの温かい腕と、そして、心地よく心の奥底まで響いていく言葉に抱かれ、ミルフィーは心の底から幸せを感じていた。
|