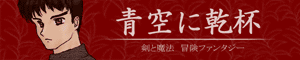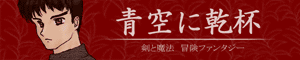|
「xxxxxx・・」
「ダメよ、そんなところ・・・」
男の声は小さすぎて聞こえなかったが、ミルフィーの声だけはしっかりカルロスに耳に入っていた。
「そんなところぉ〜・・・?」
−ブチッ!−
思わずどんなところか想像してしまったカルロスの理性もそして本能も何もかもブチ切れた!
−バッターーン!−
「ミルフィーッ!!」
乱暴に扉を開けてミルフィーの名を叫んだカルロスの目に入った光景は・・・・彼が想像していたものではなく、そこには、部屋の奥にあった外へと続くバルコニーには、・・・・コマはカルロスの知っているものと違っていたが、チェス板らしいものを置いたテーブルを挟んで座っているミルフィーと一人の男の姿があった。
「ミ、ミルフィー・・・?」
あまりにもの拍子抜けで、カルロスは戸口の所に呆然と立ちつくしていた。
「カルロス?その声は・・カルロスでしょ?」
「ど、どうしたんだ、その目は?」
カルロスの方を向いていたミルフィーの目には包帯がしてあった。
「ああ、これ?」
ふふっと軽く笑うミルフィーに、カルロスはゆっくりと近づいていく。
そして、そのカルロスと入れ替わるかのように、チェスの相手をしていた男は一礼をすると部屋から出ていった。勿論カルロスはその男になど全く気を払っていない。
「なぜだか分からないんだけど・・・」
「分からない?」
「ええ、そう。どうしてここにいるのか、それから、どうして花の中で眠っていたのか分からないんだけど・・・でも、一つだけ、はっきりとはしないけど、分かっていた事があったの。」
「なんだそれ?」
「そうよね、分からないわよね?私だって分からないんだもん。」
カルロスはミルフィーの横のイスに座ると彼女を見つめた。
「でも、どうしてだか思ったの。まだ目を開ける時じゃないって思ったのよ。」
「目を開ける時じゃない?」
「そう。まだ何も見てはいけないような気がしたの。誰かが迎えに来てくれるような気がして・・・初めて見る人はその人じゃないといけないような気がしたから。だから、最初のうちは目を閉じていたんだけど、ふとした拍子で開けてしまってもいけないでしょ?それで包帯をしたの。その人が来るまでこうしていようと思ったの。とても大切な人だと感じるの。誰なのか分からないけど、きっとそれは私にとって本当に大切な・・・・。あっ・・・」
「どうした?」
一言ひとこと考えるように話していたミルフィーは、カルロスの自分に対する気持ちを思い出し、小さくすまなさそうに言う。
「ごめんなさい。・・・こんな事、カルロスに言うべき事じゃなかったのに・・・私・・・知ってる人にようやく会えて嬉しくて、つい・・・」
それは、その言葉は、ミルフィーの記憶が、再生されたその身体の年齢までしかない事を暗示していた。
(やはり記憶はないのか?・・オレとの記憶は?)
「気にするな。」
そう答えながら一応無事だったことにほっとし、そして喜びを感じつつ、カルロスは聞いてみる。
「ミルフィー、いくつになった?」
「いくつって・・・こっちに来てから2回冬を越したから・・・20・・・あっ!」
「なんだ?」
「ご、ごめんなさい、カルロス。私、あなたを騙すようにして置いてきてしまって。」
ふっと笑ってカルロスは答える。
「ああ、いいさ。そんなこと。」
「・・・ありがと、カルロス。でも、まさかカルロスまで来るとは思っていなかったわ。銀龍と会えたの?レオンやレイムは?」
ミルフィーはここが神龍の世界だと思っていた。
「いや、オレ一人だ。」
「一人?」
「ああ。お前を迎えに来た。」
「迎えに?・・・だってまだ解決していないのに・・・。」
カルロスは膝に置かれていたミルフィーの両手をそっと包み込むように握る。
「もう!カルロスったら変わってないんだから・・・」
そう言いつつ、その手から自分の手を引こうと思ったミルフィーは、ふと感じる。
「・・・カル・・ロス?・・・・」
カルロスの手の温かさが自分の手を通って全身に伝わってくる。全てではなかったが、それは突然わき上がった清水のようにミルフィーの記憶を呼び覚ましていった。
「あ・・・・」
思わずミルフィーはカルロスの手を握り返す。その温かさを確認するかのように。記憶を自ら求めるかように。
「ミルフィー・・」
そんなミルフィーの手を、カルロスはしっかりと握りしめる。
放心したように、しばらくそのままの状態でじっとしていた後、ミルフィーは、慌てて目を覆っている包帯を取ろうと頭に手を伸ばす。
「オレが取ってやろう。」
シュッと結び目をほどき、くるくるとミルフィーの頭に巻き付けてある包帯を、カルロスは取っていく。そのカルロスの心は嬉しさで躍っていた。
(オレとの記憶がなかったのに、魂の中での事は覚えているはずはないのに、オレを待っていてくれたのか、ミルフィー・・・お前は・・)
心の中で呟きながら、カルロスは包帯をとっていた。包帯などそのままで抱きしめたいと思いつつ、が、急いで取って、とにかく目を合わせなければ安心はできない、彼女のその瞳に自分の姿を焼き付かせなければ、という思いもあった。
「ミルフィー・・・。」
包帯を取ったその顔は、ミルフィーが、その昔異世界へ旅立った時より、ほんの少し大人びた顔だった。数日前までの彼女より確かに若い。
「開けてもいいぞ、ミルフィー。」
ゆっくりと瞼が開いていく。そして、彼女の青い瞳に、見慣れたその瞳にカルロスの顔が映る。
「カルロス・・・」
「ミルフィー・・」
その瞳に涙がにじみ出、一雫零れ落ちていく。その大粒の涙を、カルロスはそっと唇で受け止める。
「カルロス・・」
カルロスの胸に飛び込み、ぎゅっと腕に力を込めて抱きついたミルフィーを、カルロスもまたぐっと抱きしめる。
「お帰り、ミルフィー。」
「カルロス・・・。」
やさしく心に響くカルロスの声を噛みしめ、ミルフィーは答える。
「ただいま・・カルロス。」
「私って・・・・」
「ん?どうした?」
バルコニーから出てそこから砂漠まで続いているオアシスの中をカルロスとミルフィーは歩いていた。その泉をふとのぞき込んだミルフィーが呟いた。
泉の淵へ座り込み、じっと水面に映った自分をミルフィーは見つめながら、顔を触る。
「私って・・・もしかして、若くなってる?」
「分かるのか?」
「当たり前でしょ。自分のことよ?」
「そうか。そうだな、確かに若返ったな。10才くらい若くなったか?」
「そんなに?」
「ああ。」
満足そうにカルロスはミルフィーを抱いて立ち上がらせる。
「ねー、カルロス。」
「なんだ?」
「カルロスは、私がどうしてあの花の中にいたのか知ってる?」
「あ、いや・・・・」
「でも、黄金の花を捜していた勇者って、あなたでしょ?」
「ま、まー、そうだが・・・・」
「ぼんやりしていた記憶が少しずつ戻っては来ているんだけど、ぜんぜん思い出せない事があるの。」
「いつ頃の記憶が思い出せないんだ?」
「・・・この世界での剣術大会が終わって・・しばらくあなたとゆっくり王宮で過ごしていたのは覚えてるの。それからが・・・ぜんぜん・・・。」
「そうか。」
「ね、カルロスなら知ってるでしょ?私、何してたの?何をしてどうなってあの花の中にいたの?・・・・若返ったし・・・。これはこれでいいんだけど。・・・カルロスは魔王を倒した勇者なのよね。私は・・・一緒じゃなかったの?」
じっと瞳を見つめて返事を待つミルフィーに、カルロスはにこっと笑う。
「んー・・・実はな・・・お前はちょっと頑張りすぎて、その時倒れてしまったんだ。」
「魔王にやられたの、私?」
「んー・・・手強かったからな。」
「闇を払う太陽の剣は?私、使わなかったの?」
「ああ・・・・」
カルロスは、そのミルフィーの言葉で思いついた話をすることにした。
「使ったんだが、勢い良すぎてな・・暴走してしまってらしい。」
「え?太陽の剣が?」
「そうだ。それで、魔王を倒したはいいんだが、ミルフィーまで倒れてしまってな。あ、いや、そうは言っても命にまでというんじゃない。ちょっと気を失っただけなんだが・・・陽の光でダメージを受けてしまったお前の身体を黄金龍が癒してくれた、とそういうわけだ。」
「そうだったの・・・。」
ミルフィーは完全にカルロスの言葉を信じきっていた。
「若返ったのはそのおまけなんだろ?」
「ふ〜ん・・・・若返るなら、時々あってもいいわね?」
「ミルフィー!?」
「あ・・・・」
きつい視線をしたカルロスに、ミルフィーはばつの悪そうな顔をして小さくなる。
「ごめんなさい。そんなのいけないわよね。・・・カルロスには心配かけてしまったし・・。」
「そうだ。どれほどオレが心配したか。だいたい癒してくれるのはいいが、お前を包んだ花がどこに出現するのかは分からないと言うんだからな。無責任ってもんじゃないか?」
「だって、世界が違うのよ。黄金龍にしてみれば、この世界までツルを延ばす事だけでも大変だったんじゃないかしら?」
「そうだな・・・そう言えばそうかもしれん。いくら神龍でも、世界が違うんだからな。」
「そう。だから、私もそんな無茶しないように気をつけるわ。1回できたからって2回目はできるかどうか分からないんだし。」
「そうだ。もう二度と無茶はしないでくれ。」
「はい。」
カルロスの微笑みに、ミルフィーも微笑んで応える。
「ミルフィー!」
「ミリア!」
遠くからミリアが駆けてくる姿を見つけ、ミルフィーは驚きながらもミリアにその微笑みを向ける。
「まったく・・・カルロスったらミルフィーが元に戻ったのなら教えてくれればいいのに?」
「いや、すまん・・・うっかり忘れていた。」
「どうせカルロスはミルフィーしか見えてないんでしょ?私のことなんかすっかり忘れてたんでしょ?」
「いや、本当にすまん、ミリア。」
「ホントにもう!誰がここまで連れてきてあげたと思ってるのよ?!」
「わ、悪かった・・・。」
「な〜〜んて・・・」
平謝りに謝るカルロスを睨んでいたミリアは、急ににっこりする。
「いいのよ、カルロス。ミルフィーが無事ならそれで。」
「ミリア・・」
「じゃ、ミルフィー、カルロスとゆっくりね。もうしばらくここで身体を休めていた方がいいわよ。」
「え、ええ・・でも、ミリアは?」
「邪魔したくないし・・私もジルに会いたいし。」
ミリアはくすっと笑ってカルロスを見た。
「そうか。」
「帰る時はまた呼んでね。」
「ああ。世話になるな。」
「そうね。本当に世話の焼けるお兄さんとお姉さんなんだから。」
「え?」
「ははは・・悪いな、ミリア。」
「じゃね♪」
ボン!とその身を炎に変え、ミリアは姿を消した。
「ミリアには何かお礼をしなくちゃね。」
「そうだな。」
彼らの要望でもあり、カルロスとミルフィーは今しばらくその神殿に滞在することにした。そして、ここにようやくカルロス待望のハネムーンの続き、2人きりでゆっくりと過ごすことができるようになった。
まだ完全に戻ったわけではなかった記憶を、ミルフィーはカルロスとの会話やちょっとした事をきっかけに、徐々に思い出していった。
そして、喉元過ぎれば何とやら・・カルロスにとってのあの例えようもないほどの絶望感も、もはや関係なかった。若返ったミルフィーを傍らに、カルロスは大いに満足していた。
が、目の前でミルフィーを連れ去られた事は、カルロスの記憶から決して消えることはないように思われた。そのおかげで、以前にも増してミルフィーに関しては、過保護というか、過干渉に陥ったらしい。
「どこへ行く、ミルフィー?お前はオレの傍にいればいいんだ。そう一人で出歩くな。」
「でも、カルロス・・・」
「それともオレがうるさいか?」
「そんな・・・そんなことないわ。」
「じゃーさっきからどうしてオレを避けてるんだ?」
「避けてなんていないわよ?」
「オレに隠れるようにしてるじゃないか?」
「・・・・」
ミルフィーは困り果てた顔でカルロスを見上げる。
「・・・カルロス・・・お手洗いも一人で行っちゃだめ?」
できれば、それも・・と思った事は確かだった。が、さすがのカルロスも、そこまでは口にしなかった。
|