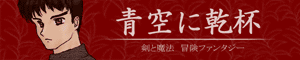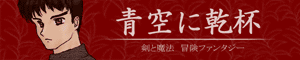|
「ここがミルフィーの魂の中か・・・・」
何もない空間だった。どこまでも荒れ果てた地が続き、凍えるような寒風が吹いていた。
「ミルフィー・・・・」
カルロスは走り始めていた。どこまでも永遠に続くかと思われるような平原を走り続けていた。
「ハーッハーッハーッ・・・・」
どのくらい走っていたのだろう。どこまで走ってもいつまで走っていても同じ景色が続いていた。
息が切れたカルロスは、しばしその場で立ちつくす。
普通なら汗まみれになっていてもいいはずの全身は、冷え切っていた。
「ミルフィーは・・・どこにいるんだ?本当にここにいるのか?」
ふとそんな考えがカルロスの脳裏をよぎる。が、次の瞬間思い直す。黄金龍が嘘をつくわけはない。そして、ふと気づく。
「そうだ。ここは、ここ自体がミルフィーの心だった。この冷たい大地も・・・吹きすさぶ寒風も、そして、どんよりした空も・・・・」
どれほど辛い思いをし、どれほど悲しみ、苦しんでいるのだろう、とカルロスは思った。
そして、すっとそこに座ると、カルロスは目を閉じてミルフィーに呼びかけ始める。
「ミルフィー・・聞こえるか、オレの声が?オレの心が聞こえるか?・・・オレの想いが届いてるか?」
まさにそこは凍てつく大地と言えた。その冷たさと冷気とも言える寒風で、カルロスの体温は急速に奪われていく。が、カルロスにはそんなことは全く気にはならない。
「ミルフィー、オレたちの愛はこんなことでどうにかなってしまうような柔な気持ちじゃないはずだ。聞こえるだろ?オレの声が。応えてくれ、ミルフィー・・!・・・一言だけでいい、そうすればオレはお前の所へとんでいく!・・・ミルフィー!!」
が、ミルフィーの返事はなかった。
「いや、届くはずだ。必ず・・・・。」
が、返事がないということは、やはりじっとしていてはだめなのだろうと思ったカルロスは再び走り始める。心の中で呼びかけながら。
「あ・・あれは?」
それからどれほどその寒風の中を走り、さすらっただろう。どこまでも平地だったそこに、遙か遠くにぽつんと塔のようなものが見えた。
「ミルフィーはあそこにいるのか?」
期待に目を輝かせ、カルロスは疲れ切った自分に鞭を打って走る。
「こ、これは・・・・?」
遠目に見えた塔のようなもの。それはまさしく憎んでも憎みきれないあの魔王の居城だった。ただ、岩山だったそれとは異なり、それは氷でできていた。荒れ狂った吹雪がその周囲を囲み、近づくものを寄せ付けまいとしていた。
「入口らしきものはどこにもない。」
猛吹雪の中、周囲を丹念に探したカルロスは、疲れと絶望感でがっくりと座り込む。
−ほわっ−
「ん?」
吹雪の中だというのに、温かさを感じ、カルロスははっとする。
「カルロス、頑張って!諦めちゃだめよ!ミルフィーを、必ずミルフィーを見つけ出して!お願い!」
カルロスの心にミリアの声が聞こえた。
「そうだ・・・こんなことで諦めては・・・」
ぐっと力を入れて立ち上がると、きっと目の前の断崖絶壁を見つめる。
「そうだ!」
懐に入れておいた蜘蛛夫人からもらった巻き糸を思い出して取り出す。
「確かに入口もそして、足がかりにできるようなくぼみも何もないように見えるが・・・これがどこかにかかれば・・・・そうすれば・・・・」
その希望に願いをかけ、カルロスは糸を自分の身体に巻き付け、巻き棒の方を思いっきり上に投げる。
が、吹雪の突風が吹き荒れるそこで、思うように投げられるわけはない。
「ダメなのか・・・?」
数回投げてみた。が、上へ行くどころか風に飛ばされ、氷壁に当たりあっけなく地面に落ちる。
絶望に浸され、巻き糸を握るカルロスの手は小刻みに震え、表情は強ばっていた。
「ミルフィー・・・オレはなんでこんなところへお前を連れてきてしまたんだろう・・・軽い気持ちだったのに・・・お前と二人っきりで幸せを感じていようと思ってしたことなのに・・・・こんな事になるとは・・・・・」
後悔の念がカルロスを襲っていた。巻き糸を握りしめた手を見つめ、カルロスは自分自身を呪っていた。
「カルロス!」
「ミルフィー?!」
一瞬ミルフィーの声が聞こえた気がし、悲しみに呆然としていたカルロスは、はっとして周りを見る。
「カルロス・・助けて・・・カル・・ロス・・・」
「ミルフィー!」
必死になって目を凝らして周囲を見ても、そこにミルフィーはいない。
「何を弱気になってるんだ!ミルフィーを助けなくてどうする?」
今一度高くそびえ立つその氷の塔をきっと見上げ、カルロスは心に誓う。
「何がなんでも助ける。今一度オレの腕にミルフィーを抱きしめるんだ!」
その決意を小さな巻き糸に、細い蜘蛛の糸に託し、カルロスは必ず道は開けると祈りと共に、心に固く信じて投げる。
「よしっ!かかった!」
再び巻き糸を投げる事数回。ピンと張って上から垂れ下がったそれは、満身の力で引いても切れる気配は、そして、落ちてくる気配はなかった。
「今、助けるからな、ミルフィー!」
猛吹雪の中、決死のロッククライミングが始まった。しかも足場は最悪状態の氷。
そして、命綱は、綱とは言えそうもないほど細い蜘蛛の糸。それでも他に手段はなかった。糸が切れないことを信じつつ、そして、感覚のなくなっていく手足に必死で力を入れ、滑りやすいその氷壁の少しでもくぼみらしい箇所を探して足を運び、カルロスは必死の思いで登った。
「ここまでか?・・・まだ半分も登っていないぞ?」
魔王の居城にあったミルフィーのいた部屋は最上部だった。巻き棒のところまでようやくの思いで登ったカルロスは、思わず上を見上げてため息をつく。
「いや・・・そんな事を言ってる場合じゃない。ミルフィーの苦しみと比べればこんなことは大したことじゃない・・。」
カルロスはともすると弱気がちになってしまう自分を叱咤すると、巻き糸を再び上へと投げる。
そして、再び登り始めたカルロスは、またしても途中で止まる。
「まだか・・・・それでも半分くらいは登っただろうか?」
吹雪で上も下も、いや、周りは全く見えない。
「ミルフィー・・・・」
疲れと寒さがカルロスを眠りの中へ誘っていった。
「ん?」
「お目覚め?カルロス?」
「・・・ここは?」
眠りから覚めたカルロスの目の前にミルフィーの微笑みがあった。
思わずがばっと身体を起こし、見渡したそこは、藍の奥神殿。カルロスは心地よい森の中でミルフィーの膝枕で寝ていたらしかった。
「オレは・・夢を見ていたのか?」
そっと立ち上がり周囲を見渡す。
「夢?」
「ああ・・・夢だ・・・・。」
「どんな夢?」
「どんな・・・・・?」
つい今し方まで見ていたはずだった。そして、はっきりしていたその夢が急にどんなものだったのか思い出せなくなり、カルロスは考え込む。ひどく悲しく、そして絶望感と後悔、自分自身を呪いたいほどの憤りを感じていたような気もしたが、はっきり思い出せない。
「よく覚えてないんだが・・・・」
「そう?」
カルロスは同じように立ち上がり、温かい笑みで自分を見つめているミルフィーに、ほっとすると同時に、その存在を確かめるべく抱きしめようと手を伸ばす。
「愛してる、ミルフィー。」
「私もよ、カルロス。」
が、その手が彼女に触れるか触れないかで、ミルフィーの姿はすうっと消える。
「ミルフィー?!」
慌てて彼女の姿を探すカルロスの周囲から、温かい森もふっと消え、闇に覆われる。
「ミルフィー?!」
その自分の叫びにはっと気づいたカルロスは、その温かい光景の方が夢だったのだと悟る。
−ヒュ〜〜〜〜〜・・・−
そこは、猛吹雪の中。細い蜘蛛の糸になんとか支えられ、カルロスは、宙づりになっていた。
「くそっ!・・・このままミルフィーを闇に落としてなるものか!」
夢の中の彼女の笑顔を思い出し、カルロスは必死になって細い糸をたぐった。
「ミルフィー!」
必死の思いで頂上近くまで登ったカルロスは、ちょうどよく見つけた窓から中に入り、通路を、そして階段を駆け登っていく。
「ここだな?!」
そしてミルフィーが囚われていると思われる部屋の扉を勢い良く体当たりして飛び込む。
「・・カル・・ロス・・」
「ミルフィー!」
「助けて・・、カルロス・・・・助け・・・・」
カルロスの目の前、そこには、蜘蛛の形の魔王に組み敷かれ、両の目に涙をためて恐怖に染まったミルフィーの姿があった。
「くそっ!ミルフィーを離せっ!」
咄嗟にカルロスは両断しようと腰に手を充てる。が、そこに剣はない。
「そうだった。剣は持って来なかったんだ。」
そう思った次の瞬間、カルロスは気を取り直す。
「剣がなくとも構わん!素手ででも奴には負けはしないっ!」
拳に怒りを込め、カルロスは突進していく。
「ミルフィー!今助けるぞ!」
が、今少しでミルフィーを羽交い締めにしている蜘蛛の足に拳を打ち付けるところだったその時、蜘蛛も、そしてミルフィーもふっと消えた。
「とっと・・・・」
不意に目標を失い、バランスを崩してカルロスは、思いっきり壁に自分を打ち付ける。
−ガツ!−
「う・・・・・」
が、その痛みより、ミルフィーが再び消えてしまった事の方がカルロスにとっては痛かった。
「ミルフィー?!・・・どこだ、どこへ行った?」
慌ててカルロスは部屋の外へ飛び出す。
「な、なんだ・・これは?どういうことだ?」
飛び出したところは、何もない平地だった。塔も吹雪もなにもない。し〜〜んと静まり返った平原がどこまでも続いている。
部屋に戻ろうと振り返ったそこには、その部屋もない。
(また振り出しに戻ってしまったのか?)
そう思い、カルロスは再び走り始める。絶望に打ちひしがれている時はなかった。すでにずいぶん時を費やしている。いい加減ミルフィーを見つけなければ、とカルロスは必死の思いで走った。
ここはミルフィーの魂、いわば心の世界。あの塔も吹雪も彼女の心を現したものだったのだろうと、ふとカルロスは思う。たとえ姿は見えなくとも、心からの呼びかけが届かないはずはない。カルロスはそう思いながら、必死で走っていた。
「ミルフィー・・・もう一度姿を見せてくれ。頼む・・・ミルフィー・・・・」
走り疲れたカルロスは、疲労と寒さで再び座り込む。
「ミルフィー・・・オレはお前がどんなになっていてもかまわん。戻ってこい。オレのところに戻ってこい。嫌な事など忘れさせてやる。このオレの腕の中で全て忘れさせてやる。・・・だから、だから、戻ってこい、ミルフィー・・・オレの所へ。オレの傍へ・・・・」
−シュルシュル−
「ん?」
不意に背後で糸を吐くような音と何かの気配を感じ、カルロスは後ろを振り向く。
「なっ?!」
そこには、あの蜘蛛がいた。カルロスにとっては憎んでも憎み足らないあの魔王が。
−ブン!−
「なに?」
カルロスは驚いて自分の手を見つめる。その彼の手には、無意識のうちに怒りで練り上げたのか、青白く光る剣があった。
「剣があれば言うことなしだ。」
ぐっと剣を握る手に力を込め、蜘蛛を睨む。
「ミルフィーの悲しみを苦しみを、思い知るがいいっ!」
だだっと駆け寄って大きく飛び上がり、カルロスは一刀両断にせんと、剣を振りかざす。
「な?」
が、その蜘蛛の瞳に涙を見つけ、カルロスは思わず剣を退く。
「ま、まさか・・ミルフィー?」
なんとか転ばずに着地すると、カルロスは蜘蛛を見つめ直す。
「ミルフィー・・か・・・・?」
その青い瞳には見覚えがあった。確かに彼女だと確信できた。
「ミルフィー・・・・・」
が、蜘蛛は明らかにカルロスを攻撃しようとしていた。鋭い歯を交差し、カルロスを突き刺すべくその鋭く尖った前足を高く上げていた。
「カルロス・・・殺して、・・お願い、私を殺して・・・・」
攻撃を予測し、身構えたカルロスの耳に声が聞こえた。力無いかすかな声だったが、確かにそれはミルフィーの声。
「ミルフィー?!・・・操られているのか?」
が、返事はない。
「ミルフィー・・・・」
その涙に濡れた青い瞳を今一度見つめ、カルロスはふっと笑うとその微笑みを浮かべたままその場にすっと座った。
「オレがお前を傷つけれるわけないだろ、ミルフィー?」
やさしく見つめながら言ったその言葉に、高く上げられていた蜘蛛の足がびくっと震えて止まる。
「だから、その牙でオレを殺してくれ。そうすればオレも同じになれるんだろ?」
止まった足はゆっくりと下ろされていく。
「ミルフィー・・・お前が闇に身を沈めるというのなら、オレもそうしよう。お前が蜘蛛に身をやつすのなら、オレも蜘蛛になろう。・・・忘れたのか?オレはどこまでもいつまでもお前の傍にいると言った。たとえお前がどのようになってもオレは構わん。別に人間にこだわりはしない。オレは、お前の傍にいれさえすれば、それでいい。お前を感じ、お前と共にいられれば、どんなところでも、何であってもオレは満足だ。お前の横がオレのいる場所なんだからな。そう言っただろ?・・・ミルフィー、お前はそれじゃいけないのか?オレと一緒だけではダメなのか?」
真剣なそして熱い想いをその瞳にたたえ、カルロスは青い瞳を見つめていた。
「・・・カル・・ロス・・・」
ふっと蜘蛛が消えると同時に、そこにはミルフィーが立っていた。あふれ出る涙を拭こうともせず、彼女はカルロスを見つめ立ちつくしていた。
「ミルフィー・・・」
飛ぶように彼女に近づくと、カルロスは思いの丈を込め抱きしめる。
「ミルフィー・・・すまん、辛い目にあわせてしまった。守ると言ったのに・・何があっても守ると言ったのに。」
「カルロス・・」
「だが、こうして戻ってきてくれた。それで・・それで、十分だ。」
カルロスは片手で彼女を抱きしめたまま、もう片方でそっとミルフィーの頬を包む。
「ミルフィー、何があろうと、どうなろうと、お前はオレの妻だ。この世で只一人の大切な女だ。オレにとってはどんな宝石よりも美しく大切な・・・。」
「私・・・」
「何も言わなくていい。全てが終わったんだ。ミルフィーが気にすることは何一つない。」
「でも、私は・・・私は魔王に・・・・」
「ミルフィー・・・誰もお前を汚せはしない。オレが・・オレの愛でそんなものなくしてやる。だから、もう気にするな。そんなことは気にせず、オレの腕の中で笑っていてくれ。その微笑みでオレを幸せにしてくれ。」
「カルロス・・・」
「誰よりも、何よりもお前はきれいだ。」
「カルロス・・・・」
ミルフィーはカルロスのその温かい腕の中で泣き始めていた。
「忘れてしまえ。いや、オレが忘れさせてやる。オレの腕の中で、オレの愛で。」
「カルロス・・」
涙で濡れた目で見上げるミルフィーをカルロスは今一度ぐっと抱きしめる。
「そんなことを考えるよりオレの事を考えていろ。オレの事だけを思っていろ。・・いつも・・・オレを愛している事だけを・・。」
そっと髪を撫でながら、カルロスはミルフィーの耳元でやさしく囁いた。
「愛してる、ミルフィー・・・。何があろうとオレの心は変わりはしない。」
|