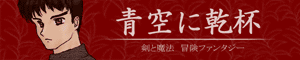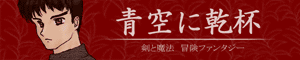|
王宮の一角にある広々とした部屋を貸し与えられたカルロスとミルフィーはゆったりとした時間を過ごしていた。加えてカルロスの思惑通り甘い時を。
「でも、いいかげん退屈よね・・・。」
あれから1週間が過ぎていた。ミルフィーはバルコニーに出て夜風にあたりながら夜空を見つめていた。
「綺麗なお月様・・・・」
手が届きそうなほど大きな満月だった。雲一つなく、満天の星空に周囲を囲まれたそこからは、まるで月光の波動さえも感じられるほどだった。
「少し恐いくらいね。」
その月光を全身に受け、ミルフィーは銀龍のことを考えていた。
「黄金龍が太陽なら銀龍は月・・月光よね?」
守るべき世界は異なってしまい、その身は離れたが心はしっかりと結ばれている2頭の神龍。
「私もカルロスとずっとそんな風でいたい。・・・この世での命が消えても魂のつながりがずっとあってほしい・・・。」
ふと無性にカルロスが恋しくなり彼の傍らに戻ろうとした時だった。
「女よ。我が元へ。」
「え?」
「どうした?」
ちょうどその時、ふと目覚めたカルロスが上体を起こす。
「ミルフィー?」
「カルロス!・・・」
淡く銀色に輝くの月光が巨大な蜘蛛の形となり、ミルフィーを捕らえていた。逃れたくても逃れることができず、ミルフィーはカルロスに両手を伸ばし助けを求めている。
「ミルフィーッ!」
咄嗟にベッドの横に立てかけてあった剣を手にし、カルロスはバルコニーへ飛ぶように駆ける。
「ミルフィーッ!」
「カルロ・・」
が、1歩間に合わず、その剣が届かず、ミルフィーは銀色の蜘蛛の姿と共にそこから消えていた。
「ミルフィーッ!?」
真っ青になったカルロスのミルフィーを呼ぶ声が辺りにこだましていた。
「どうかされましたか?」
部屋の近くをパトロールしていた衛兵がドアを開けて入ってくる。
「ミルフィー?!・・どこだ、ミルフィー?!」
そこにはバルコニーから身を乗り出してミルフィーを探すカルロスの姿があった。
「カルロス殿、では・・・」
「すまぬ。世話になりっぱなしだが、どうあってもすぐ発ちたいのだ。」
「それは構いませんが・・ミルフィー殿を連れ去った者がおわかりなのですか?」
「いや・・・はっきりと分かっているわけではないが・・・幾分心当たりがある。まずそこを当たってみるつもりだ。」
「そうですか。よろしければ兵をおつけ致しますが。」
「いや、一人の方が身軽でいい。」
カルロスは、月光が蜘蛛の形をしていたことで、まずは、森の館の蜘蛛夫人を訪ねてみることにしていた。もしかしたら彼女の夫ではないか、と思った。
カルロスは当分の保存食と幾ばくかの路銀そして馬をもらい、王子の心遣いに感謝を述べると夜の道を駆けた。
そして5日5晩、途中で馬を替えて走り続け、ようやく森の館に着く。
−バタン!−
「あら・・・カルロス様・・」
乱暴に開けて入ったカルロスの前に驚いたように彼を見つめる蜘蛛夫人がいた。
「どうかなさったのですか?奥様は?」
「ミルフィーを・・・ミルフィーをどこへやった?」
「え?」
「旦那はどこだ?」
「ま、まさか・・・・」
カルロスの血相を変えた顔とその言葉で、蜘蛛夫人も顔色を変える。
「お、お待ちください。ただいま見てまいります。」
「待て!オレも行く!」
一人奥へ行こうとした蜘蛛夫人の後にぴったりとくっつくようにして、カルロスは走る。
−バタン!−
そして、蜘蛛夫人の夫の部屋のドアを勢い良くあける。
「あ・・なた?」
そこには灰色の巨大な蜘蛛がいた。
「ミルフィーは?」
その部屋の中を焦りつつ見渡すカルロス。が、そこにミルフィーの姿はない。
「ミルフィーは?オレの妻をどこへやった?」
悲痛な表情と怒りを浮かべ、カルロスは剣を蜘蛛の夫に突きつけ叫ぶ。
「つ、妻・・・あ、あんたのか?」
「そうだ!」
「あなた!また手をだしたの?」
「い、いや・・オレはずっとここで寝てたぞ?」
「嘘をつくなっ!銀色の月光の姿となってオレたちの部屋に現れ、ミルフィーを連れ去っただろう?」
まさに斬りかからんとするカルロスに、蜘蛛は恐怖に染まる。
「ま、待ってくれ・・オレはそんなことはしていない。そんな力はない。」
「そ、そうです。」
蜘蛛夫人も焦ってカルロスを止める。
「それに、月光の姿とおっしゃられましたが、蜘蛛の形だったのでしょうか?」
「そうだ。それが?」
さーっと2人の全身から血の気が退く。
「それは・・・それは私の夫ではございません。そのような力はございません。あるとすれば・・・」
「あるとすれば?」
「魔王ジゼルヌ・・・蜘蛛と蜥蜴と蛾の形態を持つ異形の王。」
「魔王?」
「今この世界をその手にいれようとしている魔王です。・・・私たちのところへも忠誠を誓わぬかという使者が参っております。」
「で?」
「恐ろしい力を持っているのです。・・でも、私たちは自由を奪われるのが嫌で、それを・・返事を出し渋っているのです。」
「そう・・か・・・。」
もしかしたら見当違いかもしれないと思っていた。が、それでもここにミルフィーがいることを切に望みながら駆けてきた。
が、一応それなりの情報はあったものの、それは絶望的に近かった。
「で、その魔王とやらは、どこにいるんだ?」
しばしの沈黙後、カルロスが意気消沈した声色で聞く。
「北の最果ての地としか・・・・」
「北の最果ての地か・・・。」
ぐっと剣を握ってカルロスは向きを変える。
「行かれるのですか、カルロス様?」
「当たり前だ。オレが彼女をここへ連れてきた。オレは・・何があろうと守ると誓った。オレは・・・・」
「お待ちください。それではこれを。」
「これは?」
戸口で振り返ったカルロスに渡されたのは小さな巻き糸。
「失礼な事をしてしまったにも係わらず助命を聞き届けてくださったお礼です。崖など道がとぎれたときにお使いください。向こう岸まで投げることができれば糸の橋ができます。そして、後はまた糸を切ってこの巻き糸の部分をお持ちいただけば、何度でも使えます。」
「そうか。感謝する。」
「いいえ、このくらいしかできませんが。」
「オレは・・なんでミルフィーから取り上げてしまったんだ?」
カルロスは館を出たところで、聖龍の法力を封じたペンダントと炎の指輪を見つめていた。軽い気持ちで外したそれら。それがこんな大きな後悔を生むとは思いもしなかった。
「これを持っていれば多少は違っていただろうに・・。」
薄衣の夜着のままのミルフィーは、鎧も、そして剣も携えていない。
「ミルフィー・・・・」
自分の方に両手を伸ばし助けを求めているミルフィーの姿が瞼に浮かぶ。
『カルロス、助けて!・・いやー!!・・・・カルロス!助けてーー!!・・・・』
「ミルフィー?!」
ミルフィーの悲鳴が、助けを求める叫びが聞こえたような気がし、カルロスはぎくっとしてあたりを見渡す。
「くそっ!」
体裁も誇りも何もなかった。カルロスは火を起こすとその中へ炎の指輪を投げ入れた。
−バボン!−
「ミルフィーはどうしたの、カルロス?」
そこには人型で現れた火龍の少女ミリアが立っていた。
「それが・・・・・」
「ええ〜〜〜?!ミ、ミルフィーがさらわれた〜?あ、あのミルフィーが?」
「何も持っていないんだ。何も身につけてない。ミルフィーは・・・・」
「分かったわ!」
よほど強力な相手なのだろうとミリアも思う。例え何も身につけてなくとも、剣を携えていなくとも、攻撃魔法は使えるはず。藍の巫女であったミルフィーのその力は普通とは比べものにならないはずだった。それなのに、未だに何の行動もそして、何の音沙汰もない。たとえ世界は違っていても、風の精霊に頼み連絡くらいできるはずだと思われた。
そして、カルロスは曲がりなりにも藍の神殿の守護騎士の長。風の声を聞くことは可能なはずだった。
「北の最果ての地?」
「ああ。」
「行くわよ、カルロス!」
−バサッ!−
巨大な飛龍の姿へとその身を変えたミリアの背に飛び乗り、カルロスは北へと向かう。
「でも、なぜミルフィーをさらったのかしら?」
「考えられることは・・・剣術大会に出ていた魔物の中に高等魔物でもいて、その仇うちとか・・・はたまた・・・・」
「はたまた?」
「魔王がその時のミルフィーの腕に惚れ・・・連れ去ったとか・・」
「両方、あり得るわね。」
「ああ・・・。が、よく考えてみれば、前者なら連れ去る必要はない。その場で殺せばいいことだ。」
「ということは、ミルフィーを気に入って連れていったってこと?」
「その方が可能性は強いだろう。」
「・・・そうね・・・・。」
「それに。」
「それに?」
「覆うようにしてミルフィーを捕らえていた月光の蜘蛛から悪意は・・少なくともミルフィーに対しての敵意は感じられなかった。・・・そうだ・・・・敵意じゃない・・あれは・・・」
「あれは?」
その時の様子を思い出し、その時は気づかなかったその事に気づき、カルロスは愕然とする。
「確かに敵意ではない。そっと抱きしめ、包み込むような光の感じは・・・あれは、あれは・・・愛しい者に対する好意・・・いや、熱い想いだ。」
「カルロス?!そ、それじゃ・・・・」
「ああ、ミルフィーが危ない。まだ命を狙われた方がましだ。そういった危機への対処は慣れている。が・・・・・」
「相手が相手だし・・・術もどれほど利くかわからないわよね・・・・」
ミリアも事態が尋常ではない非常事態だと悟る。
その事件から数日過ぎているのに、何の連絡もないということも気になっていた。たとえ結界の中にいようと空気は、風はながれているはずである。ミルフィーが気づいているのなら、そして彼女が彼女であるなら、連絡はよこすはずだった。
連絡がないということ、それは・・最悪の場合、もはや命はないということ。そして、次は、術か何かで眠らされ続けていること・・または、それこそ考えたくもないが、なんらかの方法で魔王の思い通りにされているということ。
「ミルフィー・・・・」
心が張り裂けそうな思いで、カルロスは勢い良く風を切って飛び続けるミリアの背で、前方をきっと見つめ続ける。
その耳にはミルフィーの悲鳴のような助けを求める叫び声が響き渡っていた。
|