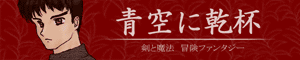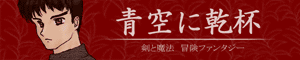|
「お前こそ、そいつと浮気してるんじゃないか?」
国都へつき、街中でようやく見つけた蜘蛛の夫からでた言葉はそれだった。
「そうだな、剣術大会でオレを負かしたら諦めてもいいかな?」
誤解だと話す2人に、男はそう答え王宮へ戻っていった。
王宮へは簡単には入れない。例え姫の花婿候補者であってもそれなりの確固とした身分がなければ、街にある宿へ泊まるしかなかった。
「すみません、おそらく夫は試合まで王宮から出てこないつもりなのでしょう。」
「らしいな。どうやら大貴族の身内に収まってるらしいな。上手く抱き込んだものだ。さてと・・・どうすべきか・・・・オレは知り合いはないし・・・。」
「私もどなたも存じ上げませんので・・。」
結局候補者として試合に参加するしかないと判断したカルロスは、ともかく参加の申し込みをするため、王宮外にある詰所に顔を出す。
「・・・思い出すな。」
場所も、そして様子も違うが、ミルフィーの時のことを思い出していた。
「あの時はミルフィーにしてやられたが・・・・」
が、今回目的は優勝ではなく、蜘蛛の夫と交える為だった。組み合わせによってはそれさえも無理ということになる。カルロスは名前を記入する前に手を止め、考えていた。
「どうかしたかね?」
「あ、いや。・・・そうだ一つ聞くが・・」
「何か?」
「闘いたい相手をこちらが指定とかはできないのか?」
「・・・・しばらくお待ち下さい。」
聞かれたことのない質問に係りは答えを詰まらせたが、そっと握らせた紙幣にそう答えると奥へ入っていく。
「お待たせいたしました。お名前が分かっていれば可能だそうです。」
「そうか。では・・・・」
「カルロス・アシューバル様。で、ご希望のお相手は?」
カルロスが記入した名前を確認すると係りは丁寧に聞く。
「確か・・・イルギス・ラ・フォンタナだったな。」
「分かりました、少々お待ち下さいませ。」
ぱらぱらとノートをめくり、手合わせが可能かどうかを調べていた係りは申し訳なさそうな顔で言った。
「申し訳ございません。その方とはすでにお相手の剣士は決まっておりまして。こちらも・・・ご指名だったようです。」
「なるほど。では、そのどちらかとの勝ち上がりとかは?」
「可能でございますが・・・噂ですと・・・」
「噂だと?」
ちょいちょいと耳をかせというような係りに、カルロスは耳を向ける。
「お相手の剣士はかなりの腕前だとお聞きしております。なんでも姫の守り役であられるマクベイン殿の従兄弟にあたられるお方だとかで。」
「ほう・・・・そんな腕なのか?」
「そういう噂でございます。」
「では、その従兄弟殿に相手を譲ってもらえればいいというわけか?」
「まー、そういうことになりますが・・・。」
「で、その従兄弟殿にお会いするにはどうしたらよいのだ?」
「はー・・・それなりのご身分の方でしたら王宮へ入られ、マクベイン様のお屋敷をおたずね下さればよろしいのですが・・・・」
「う〜〜ん・・・・当日では・・遅いよな?」
「そうでございますね。始まる前でしたらなんとかなるかもしれませんが・・・」
「そうだな・・・その従兄弟殿とやらを探して頼み込むしかないな・・・」
手をかけて悪かったな、と労をねぎらい、カルロスはそこを後にした。
「カルロス・アシューバル?」
「どうかしたのか?」
姫の宮にある庭の東屋で参加者名簿の控えに目を通していたミルフィーは、思いがけない名前を目にして思わず声をあげていた。
「い、いえ・・・ちょっと・・・。」
マクベインに慌ててそう答えたものの、ミルフィーの心臓は大きく打っていた。
(どういうこと?同姓同名?・・・それとも・・・?)
何事もこう思ったら実行せずにはいられないミルフィーは、即行動に移した。
ちょっと気になる事があるとマクベインに話し、姫の使いということにしてもらって王宮の外に出る。そして、名簿に記載されていた宿に行く。
「いないわね・・・・外に出ているのかしら?」
と思っているところにちょうど良くカルロスが姿を現す。しかも例の蜘蛛夫人がその横で人型をとっていた。
「なっ?!」
落ち着いて剣術大会へ参加した理由を聞くはずだったミルフィーは、その光景で我を忘れてしまった。
「いいわよ、そういうつもりなら・・・・」
壁の影からカルロスを見つめていたミルフィーは、即王宮へとって帰った。
そして剣術大会当日。
カルロスは競技場内の控えの間を片っ端から訪ねていた。
「いないな。まさか守り役の従兄弟だから特別扱いか?」
開始時間も迫ってきていた。諦めかけていたその時、カルロスは通路の奥を見覚えのある剣士が歩いているのを目にした。
「ま、まさか・・・・」
兜をかぶっていた。が、確かに背格好とそして、鎧もそうだが、カルロスの第六感が、夫としての本能が、それがミルフィーだと断言していた。
「ミルフィー!」
が、走り寄るカルロスを無視し、ミルフィーはすたすたと歩いていく。
「待てって、ミルフィー!オレが分からないとでも思っているのか?」
ぐいっと肩を掴むカルロスを、ミルフィーはため息をついてしばらく見つめていた。
「こっちへ。」
通路で兜を取るわけにはいかなかった。ミルフィーは奥の部屋に連れていくと、そこで兜をとり、久しぶりと思えるカルロスと目を合わせた。
「なぜあなたが・・」
「なんでお前が・・」
2人とも同時に口を開いていた。
苦笑いしてカルロスが口を切る。
「時間がないんだ。ミルフィー、姫の守り役のマクベイン殿の従兄弟とやらを知らないか?」
「それがどうかして?」
「ああ・・・簡単に説明するとだな・・・」
「ふ〜〜ん・・そういうわけね。蜘蛛のご主人ね・・。」
ミルフィーたちも一応その人物が人間ではないと疑ったのが、試合相手に選んだ理由だった。
「じゃー、カルロスに譲るわ。しっかり思い知らせてやってちょうだい。」
「は?そんな簡単にできるのか?」
「そうよ。だってマクベインの従兄弟は私ですもの。」
「は?」
「今話してる時間ないわね。」
くすっと笑うとミルフィーは付け加えた。
「ただし条件があるわ。どのみち後であなたを私の夫だと紹介しなければならなくなるでしょうから・・・決勝戦まで勝ち残ること!これが条件よ!」
「は?」
「わざと負けや不参加による失格なんて認めないわよ。」
「し、しかし・・ミルフィー・・?」
花婿になる気はないんだぞ、とカルロスの目はミルフィーに哀願していたが、彼女は全く聞く耳持たず。
「わかったわね、花婿候補、カルロス・アシューバル!決勝戦で会いましょう!」
にこっと笑うとミルフィーは再び兜をかぶり、部屋を出ていった。
「ミ、ミルフィー?」
カルロスはしばらくそこに呆然と突っ立っていた。
−ガキッ−
そして蜘蛛の夫との試合、カルロスは剣を交え声をかける。
「よー・・また会ったな!」
「お、お前は・・・?」
「美しい奥方をあんまり泣かすものじゃないぜ?」
「そう思うんだったらお前が相手していればいいだろ?」
「オレにはあんたの奥方以上の妻がいるんでな。」
「何?」
−カキーーン!−
確かにそれなりの腕はあった。が、カルロスの相手ではなかった。
「決勝戦までやらないといけないのか・・・・」
気が進まなかったがミルフィーに言われてはそうしないわけにはいかなかった。
「ふ〜〜・・・・」
勝負の決まった時点で、そっと蜘蛛夫人は夫の肩に乗せておいた。あとは2人でなんとかするだろうとカルロスは残るミルフィーとの試合だけを案じていた。
そして・・・・
「まさか、貴殿がミルフィー殿のご夫君であられたとは・・。」
「事情があったとはいえ、失礼を。」
「いやいや・・・まさに見物だった、決勝戦は。結局貴殿がミルフィー殿に勝ちを譲った形にはなったが・・まさに手に汗を握る試合だった。」
「あ・・いや・・・」
マクベインの屋敷の一室で王子とマクベインそしてカルロスとミルフィーは話していた。
王子もマクベインもカルロスがミルフィーの夫であることに納得していた。試合の時見たその剣の腕もさることながら、精悍な出で立ちと控えめだが全身からにじみ出ている雰囲気は、ただ者ではないと感じさせられた。
「お兄さま!」
「なんだ、ジョセフィーヌ・・・客人の前で失礼だぞ?」
勢い良くドアを開けて駆け込んできた王女に全員の視線がいく。
「あ・・失礼いたしました。」
いかにも儀礼的に膝を折ってカルロスに軽くお辞儀をすると、王女は早口で王子に言う。
「お兄さま、剣士様は?私の・・・剣士様はどこにいらっしゃるの?」
「何を言ってるんだ?お前はもう自由だと申したであろう?しばらくここにいて後は手はずが整い次第ジムのところへ行くのであろう?」
「え?」
「『え?』って・・そ、そなた?庭師のジムだぞ?」
「お兄さま?・・・・ジムは庭師ですのよ?」
「ですのよって・・・そのジムが良いのであろう?」
「お兄さま・・確かにジムは腕のいい庭師で、いろんなことを知ってるわ。でも、私の夫となる方は、やはり強い剣士でなくては。それに私・・・一般民のような暮らしはできませんわ。」
「あ・・・・・・」
見合っていた・・・王女以外の4人はただ呆然として見つめ合っていた。庭師のジムと一緒になりたいとばかり思っていた彼らは、呆気にとられていた。では、自分たちのした事はなんだったんだ・・心配した事は・・。
「でも、魔物は蜘蛛のご主人だけじゃなかったんだし、いいとしましょうか?」
ミルフィーの言葉に王子もそしてマクベインも頷く。
「ねー、お兄さま・・・あの方はどちらに?」
「ジョセフィーヌ?」
「はい?」
王子に会わせてくれるようせがむ王女に、ミルフィーはにっこりと笑って言った。
「あの剣士様は、あなたの傍にいつもいらっしゃる方なのですよ。」
「え?」
そう言われて、ジョセフィーヌはすっとマクベインに目を移す。
「あ・・・いえ・・そ、それは・・・・」
慌てるマクベインにミルフィーは微笑んでから付け加えた。
「あなたが望むなら庭師のジムと一緒にしてさしあげようと、偽名を使って試合に臨まれましたのよ。でも本当は・・・」
「え?・・・でも、試合でお見かけした方はビートと比べると背も低く、細かったように思えましたけど?」
不思議そうに聞くジョセフィーヌにミルフィーはにっこりと笑う。
「それは、術でそう見えるようにしてあったのよ。」
その言葉で素直なジョセフィーヌはすっかり信じ込み、その瞳には、じわっと嬉しさから来る涙がにじみ出てくる。
「ああ、ビート!あなたでしたの?・・本当にあなたでしたのね、ビート!?」
「い、いや・・・それは・・・」
「私は強い人が好きよ。私の夫になる方は一番の剣士でなくてはならないってずっと思ってました。・・でも・・でも、その方があなただったらどんなにいいかと・・どれほど思ったことか・・・私・・。」
残る3人は目配せして部屋をそっと後にした。
「しかし・・・庭師が好きになっていたのではなかったとは・・・ミルフィー殿にはとんだお骨折りをさせてしまい申し訳ない。」
「いえ、殿下、滞在中はとてもよくしてくださいましたし。お世話になってしまい私の方こそご迷惑をおかけして。」
「いや、大したことではありません。王宮にあなたを迎え、花が咲いたようでした。」
「え?」
「妹のことにしても、相手が彼なら何も言うことはない。よく機転をきかせてくださった。」
「彼の気持ちは知ってましたから。」
「なるほど。」
「で、私の気持ちは?」
「え?」
「ははは、そういうのは全く除外視のようですね。いえ、気になさらないでください。」
王宮の庭を歩きながら3人は話していた。
「どうでしょう、カルロス殿?」
「は?」
「このお礼に、今少し滞在されては?国都のあちこちでも見学されてもよいし、ここでゆっくりと過ごされるのもいいかと思うのですが。」
「よろしいのですか?」
「勿論です。ああ、そうだ。婚儀は1月後となっております。それまでいてくださるとミルフィー殿を姉のように慕っている妹も喜びます。婚儀までの期間、いろいろ妹に教えていただけるとありがたいのですが。」
「ありがとうございます、殿下。でも本当にいいのでしょうか?」
「もちろん。」
にこやかに2人の元を離れ王子は宮殿に入って行った。
「それではゆっくりとハネムーンということで・・・」
「カルロスったら・・」
カルロスの腕に包まれ口づけを受けようと目を閉じていたミルフィーは急にはっとして目を開ける。
「で、セシリアと蜘蛛夫人とはどうだったの?真っ赤なドレスがとてもお似合いな美人だったわね?」
「あ、あのな、ミルフィー・・・」
せっかくムードが高まっていたのに、とカルロスは力を落とす。
「やきもちを妬いてくれるのも嬉しいが・・・オレがお前以外の女性に目を移すことはないと分かってるだろ?」
「でも・・・」
「そういうお前はどうなんだ?」
「え?」
「さっきの王子の流し目は意味ありげだったぞ?」
「そ、そんなばかな・・。」
「こういうことはオレより鈍感だからな、ミルフィーは。間違いはないと思うが・・・問題は相手だな。」
「カ、カルロス・・・あなたが心配してるようなことはあるわけないわよ。」
「そうか?・・それにあそこまで思いっきり吹き飛ばしたネルギスとはどこまでいったんだ?」
「『どこまでいった』って・・・カルロス、いやらしいわよ?」
「怒らないから正直に言うんだ!」
「だから、カルロス、なんでもないわよ・・」
言いがかりはつけられるまえにつけろ!カルロスは先手必勝でミルフィーを責めていた。
(たまには優位に立たないとな。)
1ヶ月は2人っきりでゆっくりできる、とカルロスは顔をほころばせていた。
|