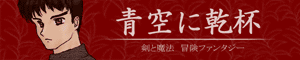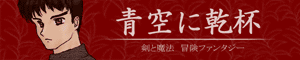|
「ここはどの辺りだ?ミルフィーはこっちに来たんじゃなかったのか?」
いつの間にか森の奥深いところへ入ってしまっていたカルロスは困り果てていた。
番兵から歩いて行ったと聞き、馬なら追いつくだろうと思い手近にあった馬に乗ってきた。そして、最初取った道がまるっきり反対方向だったらしく、そこで思いっきり時間をつぶしてしまっていた。そういうわけで、馬だったのにもかかわらず、カルロスは、ミルフィーがコインを投げて決めたあの分かれ道に来るのさえ、彼女より遅くなっていた。そして、反対の道を取ればもうこれはどうしようもない。完全にミルフィーを見失っていた。
「きゃああああ・・・・」
女性の悲鳴が耳に響き、当然のごとくカルロスは駆けつける。
「大丈夫か?!」
−ガキ!ズン!−
半獣人に襲われかけていたその少女を一太刀で助ける。
「あ、ありがとうございました。ありがとうございました・・。」
襲われた恐怖でいまだ震えながらその少女はカルロスに礼を言う。
そして、カルロスはその少女が住んでいるという館へと送っていく。
「あなたが私の娘を助けて下さった剣士様。」
森の中にひっそりとたたずむその館の主は女性だった。彼女はなまめかしいほどの女体を誇るかのような衣装に身を包んでいた。身体の線もあらわな真紅のドレスと会わせた真っ赤なルージュとパンプス。
レイラといい勝負か?思わずカルロスはそう思った。
「今日はもうまもなく日も暮れます。どうか今宵一晩この館でゆっくりと旅の疲れをお取り下さいませ。」
「そうだな。ではそうさせていただこう。」
華やかに催された宴の後、カルロスは自分のために用意された部屋から、窓の外を眺めていた。
そこから見えるのは、どこまでも続く木々と星をたたえた夜空のみ。
「どっちへ行ったらミルフィーに会えるんだ?」
カルロスはため息をつきながら呟く。
そしてゆっくりと更けていく夜の帳の中、カルロスはミルフィーの面影を抱きつつ眠りに入っていった。
「ん?」
その深夜、ぐっすり寝入っていたカルロスは人の気配で目を開ける。
「なんだ・・・?」
薬でも盛られたようなけだるさを感じながら、カルロスは目をあける。
ぼ〜っとしていた頭が、今置かれている自分の状態で幾分かはっとする。
夜着を羽織って寝たはずだったカルロスはその身に何も付けていない。しかも気配はカルロスの下半身にある。
「なにを?」
声をあげると同時にカルロスはがばっと跳ね起きる。
「あら・・・効き目が足らなかったかしら?」
カルロスのすぐ横で残念そうに微笑んだ女性は館の主。
「・・これか?」
彼女のことも気になったが、部屋中に漂っていた香の香りが気になったカルロスは素早く周囲を眺め、ベッドの枕元で煙をくゆらしていた香坪を見つけると、窓から外へ放り投げる。
「どういうことだ?」
窓の傍で新鮮な空気を吸い込みながらカルロスは未だにベッドに座っている館の主を睨む。
「あら・・恐いこと。・・・」
が、カルロスの睨みなど全く気にした風はなく、女主人はより一層なまめかしい笑みを投げかけながらベッドを下りて近づく。
「そんなにいけない事かしら?」
「そうならわざわざ香を焚いて痺れさせなくともいいだろう?」
「ふふっ・・・なかなか強そうな精神力だったから、この方がいいかしらと思いましたのよ?」
「こうやっていつも男を連れ込んで、餌食にしているのか?」
にこやかに微笑む女主人をカルロスは睨みつける。
「餌食だなどと・・・聞こえが悪いですわよ、剣士様。男と女、お互い心ゆくまで楽しむ。それがなぜ悪いのです?」
「その気のある奴を誘ってくれ。オレはそんな気は全くない。」
「あら・・・そんな冷たいことをおっしゃらないで。ね、剣士様?」
「とにかく出ていってくれ!オレは失礼させて貰う。」
「まだ夜は長いですのよ?これからでも十分楽しめますわ。」
「いいといったらいいんだっ!」
ギン!と眼を飛ばしたカルロスに、さすがの女主人も寒気を感じる。
「・・・残念ですわ・・・あなたのような方は初めてですのに・・私、とても・・・」
「いいから出て行けっ!」
拒絶されたのが信じられないというような表情で、彼女はしぶしぶドアを開けるとカルロスを今一度振り返る。そして、変わらず睨み付けているカルロスに、ため息をつきながら部屋から出てドアを閉めた。
「・・・まったく・・・・・女難の相でも出てるのか?」
つぶやきながらカルロスは手早く身支度すると、館を出るため乱暴にドアを開けた。
「な、なんだこれは?」
確かに館の一室だったはずだった。そこには階段に続く廊下があるはずだった。が、そこは真っ暗な洞窟。しかも周囲は蜘蛛の糸のようなものでびっしりと覆われている。
「オレは・・・怪かしか何かに囚われていたのか?」
部屋の中を振り返ると、さっきまで立派な作りの部屋だったそこは、同じように糸で覆われた空洞となっていた。ベッドや家具は、形でおそらくそうだろうと思わえる繭のようなものと変わり果てていた。
「・・・間違いないということか・・・。この森に巣くう魔物かはたまた物の怪か?」
ぐっと剣の柄を握りしめ、カルロスは細心の注意を払いつつ、廊下だったそこへ出る。
−グズズ・・・−
と同時に、部屋のドアはその形を崩して消滅する。
「なるほど・・・この迷路を抜けろということか。」
あちこちに枝分かれしたその通路はどこまで行っても同じだった。
しーんと静まり返ったその洞窟の中、カルロスは、いつ何があってもいいように、体力を温存しつつなるべく速く歩いていた。
が、本当に出口がない。しかも普通より疲労が激しい。その洞窟自体がカルロスの体力を吸収していると思われた。
徐々に疲労がカルロスを襲い、どれほど歩き回ったのか感覚もなくなってくる。
トッと壁にその身をもたれかけ、カルロスはしばらく立ち止まった。
「つまり・・・従わない奴は枯れて死ねということか・・・もしくは倒れて動けなくなったところを襲うとか?・・・が、オレはこんなところで倒れるわけにはいかない。・・何があっても先には逝かないとミルフィーと誓い合った。オレはいつも彼女の傍にいると・・・。」
気が遠くなってくる感じを受けながら、カルロスは必死で自分を奮い起こしていた。
−ズズズ・・・−
そんな状態のカルロスの目の前に、黒く大きな物体が現れる。
「ようやくお出ましか?」
半ば霞んでしまっていた視界の中に、巨大な真っ黒な蜘蛛が見えた。
「やはり蜘蛛か・・・上手く化けていたものだ・・・。」
剣を杖にし、カルロスは体勢を取りながら蜘蛛を睨む。
ぼんやりとその蜘蛛の全面に女主人の姿が浮かぶ。
「心を入れ替えて下さるというのなら今一度チャンスをあげましてよ、剣士様。このまま枯れさすには欲しいですわ。」
「何度言われても答えは同じだ。オレが愛する女は一人だけだ。」
「・・・強情も程々になさった方がよろしいのに。・・・残念ですわね。」
すうっと女の姿が消える。
と同時に、巨大な蜘蛛はその鋭い牙をむき、カルロスに向かってくる。
「くっ・・・ここまで体力を削られていては・・・・」
それでもカルロスは渾身の力を振り絞って蜘蛛に挑む。
「オレは・・・何がなんでもミルフィーの元へ帰るんだっ!」
−ガチッ!ギン!−
一差しで殺されそうなその牙を両手に持った剣で受け止める。
−グググッ・・−
が、それにより両手を固定されたカルロスを、蜘蛛の前足が伸びる。鋭く尖った
それで一突きにすべく高く上げる。
「ミルフィー・・・・!」
−ダン!・・ザシュッ!−
間一髪。串刺しにされるところを、カルロスは必死の思いで蜘蛛をその剣で弾いていた。
そして、それまで忘れていた聖龍のペンダントを握りしめる。
−ぱあああああ・・・−
淡い光に包まれる共に、カルロスは回復する。
「行くぞっ!」
いつものカルロスに戻れば、たとえ巨大蜘蛛だろうと相手ではない。
襲いかかる足を次々に切り落とし、あっという間に蜘蛛を追いつめていく。
「ま、待ってっ!剣士様!」
牙を折られ、ほとんど足もないような惨めな恰好となったその蜘蛛は、今再び女の姿を浮かび上がらせ、カルロスに懇願する。
「何を今更?」
止めを刺そうと剣を振りかざした時、周囲から十数匹の子蜘蛛が一斉に現れ巨大な蜘蛛を覆った。
「ごめんなさい、剣士様。お願いです、母を・・母を許してください。」
子蜘蛛を代表し、カルロスが助けた少女が涙を流して懇願する。
「お願いです!父が・・父さえいれば、このようなこともしないはずなんです。お願いです!」
胸で両手を合わせ必死に叫ぶ少女の姿の子蜘蛛に、カルロスは思わず剣を退いていた。
「で・・・・人間の姫を娶ろうと剣術大会に行った?」
「は、はい・・・・・」
元の屋敷に戻ったそこで、カルロスは身体中包帯でぐるぐる巻きの巨大蜘蛛のなれの果て、女主人と、その娘たちを前に話していた。
「私たちはこの森に住む蜘蛛。人間に害を及ぼそうなどとは思っておりません。ここで静かに暮らして行ければそれで幸せなのです。でも・・・あの人が行ってしまって・・私、寂しくて・・・・どうしようもなくて・・・・・」
呆れ返っていた。カルロスはひたすらその女主人の夫に呆れ返り、そして、彼女に同情を覚えていた。
「分かった。旦那の目を覚ましてやろう。が・・・その身体は大丈夫なのか?」
「ご心配ありがとうございます。1週間もすれば治ると思いますので。」
ほっとしたように微笑み、彼女は礼を言った。
「たいした回復力だな。」
「巣で休めば、吸収させていただいた剣士様の体力で。」
「な・・なるほど・・・それが回復剤か・・・・。」
「回復するまでご滞在くださいますでしょうか?私は遠くまで移動できませんし。」
「移動できないって、あんたも行くつもりか?」
「でなければ剣士様も方角がおわかりになられないのでは?」
「まーそうだが・・・あんたは分かるのか?」
「はい。夫の気をたどっていけば・・・」
「なるほどな。」
ふとカルロスはミルフィーの気がたどれたらどんなにいいか、と思ってしまった。
「で、剣士様、お礼とお詫びにその、剣士様の只一人の女性という方をなんとかお探ししてさしあげたいと思うのですが。」
「できるのか?」
「その女性の身につけていたものでもお持ちでしょうか?」
「ああ、ある。」
「それでしたら心配はございません。主人に会い、それを見せれば分かるはずなのです。」
「ほう・・・嗅覚か?すごいな。」
「ただ・・・」
「ただ?」
「気の多い主人がもしかすると・・・・・」
申し訳なさそうに、そして心配そうな表情で言う女主人に、カルロスはにやっと笑う。
「彼女はオレより手強いぞ。」
「そ、そうなのですか?」
「ああ・・・普通に迫るくらいなら風で飛ばされるくらいだろうが・・・いきなり襲いかかったなんてことをしたら、それこそ一瞬でみじん切りだな。」
「み、みじん切り・・・・・」
思わずぞっとする女主人。
「け、剣士様の愛しい女性とは・・・一体どのような?」
「そうだな。剣士としては最高の腕を持ち、そして、女性としては、やさしさと意志の強さと深い愛を持つ、オレにとっては只一人のかけがえのない女性だ。」
「本当に愛していらっしゃるんですね。」
「ん?そうだな・・・昔からオレは彼女にべた惚れだからな。」
うらやましそうな瞳で見つめる女主人に、カルロスは照れ笑いとも苦笑いともとれる笑みを見せた。
そして、それから約1週間後、カルロスは5cmほどに小さくその身を縮めた女主人である蜘蛛を肩に乗せ、勢い良く馬を走らせていた。
|