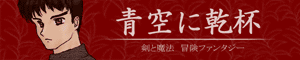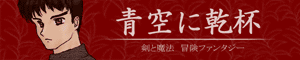「な・・・・・」
そして、崩れるミルフィーを無意識に左手で抱き留めたカルロスは、その時ようやく己を取り戻した。
「ど、どういうことだ・・これは?」
飛び散ったミルフィーの血が口に入っていた。その塩辛さと、あちこちにかかった血の温かさで我を取り戻したのである。
「ミルフィー?!」
−ガチャ−
手にしていた剣を落とし、その手もミルフィーの身体に添え、抱きしめて揺する。
「ミルフィー!しっかりするんだ!ミルフィー?!」
(オレが・・・オレがやったのか・・・・オレがミルフィーを?)
状況から判断してそうとしか考えられなかった。
(なぜだ?!なぜオレはこんなことを?!)
ミルフィーの身体から流れ続ける血に恐怖を感じながら、やはりその血を受けて赤く染まってしまっている自分の上着で彼女の身体をしっかりと巻き、回復呪文を唱え続ける。
必要以上だろうがなんだろうが、この際問題ではなかった。その弱々しく今にも止まりそうな鼓動が再び元気に打ち始めるまで、ミルフィーが助かると確信できるまでカルロスは続けていた。
「う・・ん?」
「ミルフィー?」
「・・・あ・・・えっと・・・・・・あの?・・私・・・?」
「よかった、ミルフィー・・本当に・・よかった・・・」
気づいたミルフィーをカルロスは抱きしめたかった。抱きしめてミルフィーが生きているということをかみしめたかった、が、そんなことをしようものなら勢い良く彼女の平手が返って・・いや、ミルフィーがそんなことをさせてくれることはない、抱きしめられる前に避けるはずだった。いつもの拒絶するような視線と共に、今回はそこに怒りも込められているはずだとカルロスは当然のこととして感じる。抱きしめたいのはやまやまだが、それは思いとどまるしかない。
「ミルフィー?」
が、少し様子が違うとカルロスは感じ、上体をゆっくりと起こしたもののぼんやりとしているミルフィーのその手を自分の両手でそっと包んでみる。
いつもならそれも許されず、ミルフィーはさっと手を引くはずである。
「私・・・ミルフィーって言うの?」
「は?」
カルロスの手の中にすっぽりと入った両手を引くわけでもなく、ミルフィーはじっとカルロスを見つめて聞いた。
「ミル・・・フィー・・?」
「あなたは・・・誰?」
「あ・・・、お、覚えてない・・のか?」
「私・・・・」
カルロスの手から自分の手をゆっくりと引くと、ミルフィーは両手で頭を抱える。
「わからない・・・・何も・・何も分からない・・」
「ミルフィー!」
両手で頭をかかえたまま、記憶を手繰ろうとしたミルフィーは、空白のそれに恐怖
を感じて蒼白になる。
「わからないの!何も・・・私は・・私はだれ?私は?」
そして、血塗れの自分にミルフィーのその恐怖は一気に増す。
「あ・・・これ?・・どうしたの?・・私は・・・・あなたは・・なに?・・これは・・何があったの?・・・私は・・・?」
「ミルフィー!」
恐怖に染まったその瞳で不安そうにそしてすがりつくように見つめるミルフィーをカルロスは思わずその胸にぎゅっと抱きしめる。
「大丈夫だ・・大丈夫だから、落ち着くんだ・・オレがついている。オレが・・・」
が、カルロスも又動揺していた。それまでになかったほどの動揺を。
全てが自分が原因でなったこの事態。我を忘れるほどの酔いと、確かに、その時
何者かが自分の中へ入ったように感じた。狂気による支配はそのあとだった、と
カルロスはミルフィーを抱きしめながら思い出していた。
そして、この事態をどう収拾付けようか、記憶を失ってしまったミルフィーをどうしたらいいのか・・どうしたら記憶が戻るのか、それと同時に腕の中のミルフィーにカルロスはミルフィアを思い浮かべていた。
確かに、腕の中で震えている少女は、ミルフィーというよりミルフィアだと感じていた。その場所には決して甘んじないだろうと思われた愛しい少女がいた。
−コンコン!−
血塗れでさえなかったら、そのまま抱きしめていたかったが、そうもいかない。
シャワーと着替えの為、少し落ち着いてからミルフィーを部屋まで送ったカルロスは、自分もシャワーを浴びて着替え、適度な時間を見計らってミルフィーの部屋のドアをノックする。
−カチャリ−
「・・・」
中からドアを開けたミルフィーは、心細そうな目でカルロスを見上げていた。
「落ち着いたか?」
「・・・」
気づいたときより落ち着いてはいたが、それでも不安そうに目を伏せたミルフィーを目の前にし、カルロスはこれ以上ないほど心が痛む。
「ミルフィー・・・」
「カルロス・・私・・・」
全身で不安を訴えているミルフィーを、カルロスがそのままにしておけるわけはなかった。
記憶は何もない。自分の名前もそして今口にしたカルロスの名前も、記憶からではなく、それはカルロスがミルフィーに教えたもの。
その状況がどれほど不安で心細いものなのだろう、カルロスは、思わずミルフィーを抱き寄せていた。
「ミルフィー。」
腕の中でじっとしているミルフィーが愛しく感じられた。それまで以上に。
そのままベッドへ、という考えもカルロスの頭に浮かんだことは確かだった。が、
次に浮かんだ思い、記憶のないミルフィーをそうすることは、卑怯極まりないことだと、カルロスはそれを否定した。
それでも戸口でそうしているわけにもいかない。カルロスは少し腕の力を抜くと、再び見上げたミルフィーに安心するようにと微笑んでから部屋の中・・は止めて、宿の一角にある酒場へと連れていった。
閉めるところだった酒場の主人は、訳ありと感じたのか気を利かしてカウンターに座った2人の前に勝手にやってくれとでもいうように、ボトルとグラス、そして氷の入ったガラスの容器を置くと奥へと入っていった。
「1杯どうだ?」
その問いにこくんと軽く頷いたミルフィーを見つめながら、カルロスはグラスにワインを注ぐ。
−カラン−
薄暗い酒場。カウンターを照らすランプの炎に揺れ、ワインの中の氷が光を反射して輝く。
ミルフィーはそっとそのグラスを手に取る。
「私はミルフィーで、あなたはカルロスで・・・一緒に旅をしてる・・のよね?」
「ああ。」
同じ冒険仲間であるレイミアスもレオンも故郷へ帰っていた。そして、なによりも2人は今、自分たちの世界、厳密に言えばミルフィーの世界だが、そこを離れ異世界を旅していた。術で記憶を取り戻させようと思っても、その術者を知らない。この世界にそういった術を使える人物がいるのかどうかもわからない。元の世界へ戻れば該当者はいるのだがそれも現状ではできない。銀龍に頼むことは一番最初にカルロスの頭に浮かんだが、カルロスには銀龍との接点がない。会うことも意識を通じさせることも不可能である。方法が全くわからない。
しばらくワイングラスを見つめていた後ミルフィーは自分に言い聞かせるように言った。
「あれは・・何かに襲われたの、私?」
「あ・・いや・・それは・・・・・」
この状態で、あれはオレが襲ったのだとはカルロスには言えなかった。
いや、普通の状態で言ったとしても、後が恐いことは確かだが、この状態では特に言うべきではないだろうと判断していた。
そして、その事について話そうとしないカルロスに、ミルフィーはその時の恐怖を思い起こさないようにとの優しさなのだとうと判断し、それ以上聞くことは止めることにした。
が、男女2人旅ということは、恋人なのだろうか、とミルフィーは考えていた。
やさしく気遣ってくれるカルロスの態度や視線からは、間違いなく自分に対しての好意が感じられた。
(でも、部屋が別って?)
恋人ではないのか?とふと思う。が、それは記憶を無くしてしまっている自分に対しての気遣いなのだろう、とミルフィーは判断した。慌ててもう一部屋を借りたのかもしれない。それとも恋人という関係には至ってなかったのか。
「どうかしたか?」
「あ・・ううん・・」
本当に恋人だったのか、自分はどう思ってたのか、そう考えているうちに、じっと
カルロスを見つめてしまっていたミルフィーは、頬を染めながら慌てて目を伏せる。
意識しなくとも、胸がときめいてしまうほどの整ったその顔立ちと全身からにじみ出ている雰囲気は・・・記憶があろうがなかろうが、いや、ないからこそ、今ミルフィーは純粋にそれを感じていた。無意識に、惹き込まれたようにじっと見入ってしまっていた自分が恥ずかしかった。
そして、そんな中、不意にかけられたカルロスに言葉に、ミルフィーの心臓は大きく踊った。
が、そのミルフィーとは反対に、カルロスは、その反応に喜びを感じてもいた。
不安はもちろんあったが、そのいかにも少女らしいそして初々しい反応は、男心をくすぐってもいた。
状況が状況でなければ、これ以上嬉しく、そして満足感を感じることはない。
そう、呪わしきは、その状況なのである。カルロスは困惑していた。複雑な思いでミルフィーを見、そして気遣っていた。今後どうすればいいのか、と。
そして、それはミルフィーも同じだった。
静まり返った酒場。揺れるランプの炎が2人を照らす。
2人とも何をどう話していいのかわからず、沈黙のまま時はゆっくりと過ぎていった。
|