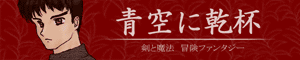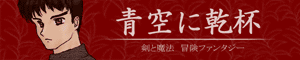|
「よー、カルロス!異世界でのたれ死んだかと思ったら元気だったんだな?」
「ああ、アルブレヒトか。お前も元気だったようだな?」
「ああ、なんとかな。」
「だけど、まさか異世界へ行ってるとは思わなかったぜ。少なくともこの世界のどこかにいるものだとばかり・・。」
「そうだな。オレもまさかそこまで行こうとも、行けるとも思わなかったが・・・不思議だな、世界なんてものは。」
「はははっ!カルロス、落ち着いたな、お前?」
「そうか?」
「ああ。」
アルブレヒトは、誰あろうこの国の第二王子。幼少の頃からカルロスとは幼なじみとして育ち、公の場以外は、タメ口である。王位を次ぐ必要がないからと割り切った彼は、結構庶民派であり型破りの王子として有名だった。
 |
ハコさんからいただいたカルロスです。
上のバナーもいただきましたっ!
ありがとうございます!! |
「なー、アル・・」
アルブレヒトの私室で思いで話に花を咲かせながら、酒を酌み交わしていたカルロスが、不意に神妙な面もちで言う。
「なんだ?急に改まって?」
「あ、いや・・・・つまり・・・その・・」
「なんだ、なんだ?オレとお前の仲だろ?何遠慮してんだ?」
アルブレヒトは笑う。
「あ、いや・・つまりだな・・。陛下に婚儀までここに滞在するようにと言われたのだが・・・。」
「ふ、ふ〜〜ん・・・・」
カルロスの顔をのぞき込むようにしてアルブレヒトは、にやっと笑う。
「確かミルフィー王女とか言ったな?」
「あ、ああ・・。」
「オレはちょうど留守で会わなかったんだが・・・なかなか落ち着いて堂々とした姫らしいじゃないか?」
「ああ、まーな。」
「で・・・婚儀までの数日、彼女を一人にしておくのが心配でたまらないから、なんとか帰れるようにオレから言って欲しいってか?」
「・・・・」
分かってるなら確認しなくてもいいだろ?と言うようなカルロスの目に、アルブレヒトはまたしても笑う。
「・・・変わったな・・・お前が一人の姫にそこまで入れ込むとは・・・」
「どうとでも言ってくれ。彼女は、・・彼女は、オレの全てなんだ。」
「お?・・・・・ホントに本気なんだな。」
驚き呆れたようなアルブレヒトに、カルロスは思わず照れる。
「だから、帰れるように陛下に進言してくれないか?ようやく想いが叶ったところなんだ。オレは彼女の傍にいたい。」
「ホントにお前、カルロスか?」
たかが女一人にそこまで、と、半ば呆れたような表情のアルブレヒトに、分かってもらえそうもないと感じたカルロスは、イスを立つ。
「違うと思うならそれでいい。・・悪かったな、時間を取らせて。」
「お、おい!カルロス!?」
すっと戸口に向かうカルロスを、アルブレヒトは追いかけて肩を掴む。
「待てって!父は意地悪でそうしてるんじゃないんだ。」
「それならどういうつもりなんだ?」
ドアの取っ手にかけかけた手を戻し、カルロスはアルブレヒトを見る。
「お前たちもう一緒に生活してるんだろ?」
「ああ、もちろんだ。」
「だから、一応だな・・・婚儀ということで、区切りというか・・・禊ぎ的なものというか・・・少しそういった期間を設けて、新たな気持ちで式に臨んでもらおうという配慮らしいんだ。」
「・・・・そういうものなのか?」
「ああ。だから少し落ち着け。言い過ぎたことは謝る。今少し話していかないか?」
「そうだな。そういうことなら。」
完全に納得したわけではなかったが、そういうものなのかもしれない、と思ったカルロスは、王宮まで付き従ってきていたジルにその旨と、そして、ミルフィーの事を頼み、再びアルブレヒトとあれこれ話をし始めた。
「しかし、会ってみたいものだな、お前をここまで夢中にさせたその姫に。まー、婚儀が終われば当然会えるだろうが。が・・しかし・・・・」
「いや、お前には合わないだろ。」
「ん?なんだ、警戒してるのか?」
はははっと笑い、アルブレヒトはからかうかのような視線をカルロスに向ける。
「そうじゃないが・・・実は王宮育ちではないしな。」
「そうなのか?しかし父には・・」
驚いたように聞いたアルブレヒトに、カルロスは苦笑いする。
「王家の姫ということは確かだ。だが、いろいろ事情があってな。」
「なるほど。・・しかし、大丈夫なのか?」
「何が?」
「王宮育ちでもない姫にアシューバル家の女主人が務まるのか?」
ガタン!と音をたて、カルロスは立ち上がっていた。
「お前までそんなことを言うのか?お前は・・・お前なら・・・」
アルブレヒトを睨んでいたカルロスの目が悲しげに陰る。
「イヤ・・・所詮、分かってもらえるはずはなかったな。ミルフィーの時同様に・・・・・こういうところで生まれ育った者に、分かってもらおうという方が間違いだ。」
「何言ってるんだ?お前だってそうだろ?」
「それはそうだが。オレは・・・家がいやで飛び出した。・・そして、自由を知り・・・彼女と出会った。」
「それはそうだが・・分かってるはずだ、アシューバル家がどういうものなのか?国におけるその存在価値がどれほどのものかを?」
「・・・ともかく婚儀の日まではおとなしくしていよう。だが、終わったら、オレは自由にさせてもらう。彼女は、ここにいるべき人物じゃないし、オレは彼女なしではいられない。」
「お、おい?カルロス?」
バタンとドアを閉めて出ていったカルロスを、アルブレヒトは呆れたように見つめていた。
「まるで人違いといってもおかしくないようだな。・・・・本当に、オレと競うようにして諸侯の姫や町娘を落としていたあのカルロスか?」
「ミルフィー・・今頃どうしてる?・・・もう休んだか?」
自分に与えられた豪華な貴賓室で、ごろりと寝台に身体を横たえながら、カルロスは一人ミルフィーの元へ心をとばしていた。
そして、待ちに待った婚儀の日。
「アシューバル公爵様、花嫁のご到着でございます。」
「承知した。」
婚礼衣装に身を包んだカルロスは、ぐっと力を込めて愛剣を腰に差すと、指定された部屋へと向かう。
ようやくミルフィーと会える、と喜びながら。
そして、豪奢な花嫁衣装に身を包んだ彼女の手を取り、カルロスは王宮内の神殿へと足を進める。多少、彼女がいつもと違うような気がしたカルロスだったが、故郷でのそして、正式な婚儀ということもあり、そう感じるのはきっと自分自身の緊張と喜びからなのだろう、と思い込み、さほど気にかけることもしなかった。ベールを取れば、その花嫁衣装のミルフィーがどんなに輝くばかりに美しいのだろう、などと思いつつ、カルロスは鼻の下を伸ばして歩いていた。
そして・・・隣の花嫁がミルフィーではないことが分かり愕然とする。
なぜ、最初花嫁の手を取ったとき感じた疑問を追求しなかったのだ、と心底後悔しつつ、そして、一生の不覚だと悔やみつつ、素知らぬ顔のミルフィーと、激怒して山のようにお説教するミリアにカルロスはただひたすら謝った。そこには恥も外聞もない。
「あ、あれは・・・何でございましょう?・・・・遠くの空から何か飛んでまいりますわ。」
「ん?」
ジルの取りなしもあってなんとか2人の怒りも一応収まった少し後、隣国のとある伯爵家に逗留していたアルブレヒトは、中庭で隣に座っている令嬢に言われて空を見上げる。
「なんだ?」
不思議に思って見ていると、少しずつ近づいてくるそれが、背に剣士2人を乗せた飛龍だとわかる。一人の甲冑は黄金に輝いている。
「ま、まさか・・・神龍・・・と黄金の剣士?」
「で、殿下・・・・」
なぜ神話の神龍と黄金の剣士がこんなところに、いや、実際に存在するなどとは考えたこともなかった。それなのに、それが実在し、そして、間違いなく自分たちのところへ向かってきている。
アルブレヒトと伯爵令嬢、周りにいた召使いらは、恐怖にも似た緊張感に支配されながらその場に立ちつくしていた。
−バサッ−
ゆっくりと目の前に下りる飛龍、そして、たっと飛び下りる剣士の顔をみて、アルブレヒトはまたしても驚く。
「カ、カルロス?」
「え?」
令嬢も神龍の剣士と知り合いなのか?と驚いてアルブレヒトを見つめる。
「一応約束だったからな。帰る前に妻を紹介しておこうと思ってな。」
「つ、妻?」
「そうだ。」
誇らしげに微笑むカルロスの横に、すっと黄金の剣士が肩を並べる。
「お、黄金の剣士が・・・お、お前の妻?・・・救世の神龍の剣士が・・・・?」
驚愕のあまり、これ以上大きく開けることができないというほど、大きく目を見開き、アルブレヒトはどもっていた。
にっこり笑った黄金の剣士は確かに女性だとそこに居合わせた人々はその姿から確信する。柔らかそうな髪を風にそよがせ、アルブレヒトを見つめる真っ青な瞳は、どこまでも澄んだ青空のような輝きを放ち、穏やかな暖かさと、そして、確固たる意志の光を秘めていた。
「あ・・あの・・・・」
アルブレヒトは、魅せられたようにミルフィーを見つめていた。いつもの女性の心を浮き立たせる賛辞の言葉が出ない。
その昔、同じ美姫を競うようにして落としていた2人は、結局趣味が同じなのである。
「じゃーな、アル。もう二度と会うこともないだろうが・・元気でな。」
ミルフィーを馬鹿にしていたようだが、どうだ?オレの勝ちだな、とでもいうような満足げな笑みをみせるカルロスに、アルブレヒトははっとする。
「あ・・お、おい?家は?公爵家は?」
「陛下に新しい主をたてるように頼んでおいたが、よかったらお前にやるぞ?」
「は?」
−バサッ−
そして、再び飛龍に乗り、ミルフィーをその腕に抱えるようにして、カルロスは空高く飛びたつ。
−バサッ、バサッ・・−
大きく羽ばたき、ゆっくりと空のかなたへ飛び去っていく飛龍を、アルブレヒトも、令嬢も、周りにいた召使いらも、そして、飛龍の姿を見つけ近くまで駆け寄ってきた人々も、呆然としていつまでも見つめ続けていた。
|